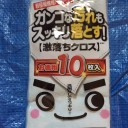Shimano ULTEGRA FC-6800
2017年9月3日 自転車・工具
改造ネタはしばらくなさそうとか言っときながらすぐにありました。
ShimanoのULTEGRAが6800系からR8000系に刷新されたことで、6800系が在庫処分で安く出回ってます。
自分的には105でも充分かなと思いますが、折角安く手に入るのでクランクを換えようと思いました。
105 5800系とは同世代なので互換性ももちろん問題なしです。
今使ってるのは完成車のままの105 FC-5800 52–36T 170mm、所謂セミコンパクトクランクというやつです。
スプロケは完成車から12–25Tですが、105 CS-5800からULTEGRA CS-6800に換えてます。
インナー36Tはヒルクライムもインナーロー36–25Tでまぁまぁってところ。
ここぞはダンシングで乗り切るので不自由はしてませんが、もうちょい軽いギア比があったら嬉しいかなって感じです。
アウター52Tが微妙。アウタートップ52–12Tはめったに使わない。
フラットではそんな脚力もなければ、ダウンヒルはビビって回せない。
やや下りで追い風で精々13Tまでかなってところ。
12–25Tは12–13–14–15–16–17–18–19–21–23–25なんで、90rpmで30km/h近辺のギア比2.6辺り(52–20T)がないんですよね。
いつも52–21Tだと軽くて52–19Tだと重いってシチュエーションが頻繁にあります。
というわけで、前からコンパクトクランク50–34Tにしてみたいと思ってた訳です。
インナーロー34–25Tはやや軽くなるし、アウターは50–19T(ギア比2.63)が使えます。
Wiggleでなぜか50–34T(170mm)だけ他より安いので、ちょうどいい機会なので購入しました。
(9/1現在もまだ価格は変わってません)
なんか、偉そうな箱に入ってますね。流石ULTEGRAってとこか。
#スプロケはショボかったような
工具はこんな感じ。後述しますがフロントディレイラーもいじります。
・クランク取付工具 Shimano TL-FC16
クランクキャップを付け外しするやつです。
・ヘキサゴンレンチ PB 2212LH-10
左クランクの脱着に5mmを使用します。
フロントディレイラーの固定も5mmです。
ケーブルの固定は4mmです。
・トルクドライバー Park Tool ATD-1
フロントディレイラーの固定は5–7N⋅mなので6N⋅m、ケーブル固定は6–8N⋅mなのでATD-1上限の6N⋅mにします。
・PH1ドライバー PB 8190-1-80
フロントディレイラーの可動域調整に使用します。
・3/8"spヘキサゴンソケット HAZET 8801K
ヘキサゴンソケットは当然定番のHAZET。
・3/8"sqラチェットハンドル Snap-on FH936A
あるとディレイラー固定位置の微調整の緩め締めの繰り返し時に便利です。
・3/8"sqトルクレンチ 東日 MTQL40N
左クランクの固定ボルトの規定トルクは12–14N⋅mなので13N⋅mにします。
クランクの交換作業は
http://hd28with4capo.diarynote.jp/201704200000375005/
に書いた感じで。
アウターのサイズが変わるのでフロントディレイラーの再調整が必要です。
フロントディレイラーの位置極めは
http://hd28with4capo.diarynote.jp/201704232036005704/
フロントディレイラーの調整は
http://hd28with4capo.diarynote.jp/201610221737065252/
の通りです。
チェーンの長さも調整が必要なこともありますが、今回は必要ありませんでした。
さてさて、千歳まで走って来ましたが、アウター50Tはとてもいい感じです。
狙い通り17–18–19Tの辺りが使いやすくなりました。
巡行中のちょっとした勾配の変化で1Tだけシフトを上げ下げするのがクロスレシオのいいところですからね〜
高速時もトップまで使えました。
50–12Tだと50km/h超えたときに回りきってしまうシチュエーションもありましたが、100rpmほど回して乗り切れたので問題はなさそうです。
急勾配の上りはなかったので、インナー34Tはまだ分かりません。
次に手稲山にでも登ったときですかね。
クランクの剛性感も105→ULTEGRAでかなり良くなりました。
回転系なので軽量化の恩恵も大きく、回しやすくなった感じがします。
スプロケを105→ULTEGRAに変えたときは、全く差が分からなかったんですが、クランクのアップグレードは結構変わるものですね。
一番嬉しかったのは、チェーンリングが全くフレていないことですね。
FC-5800は少しフレていたので、シフトケーブルの張りを調整しても、アウタートップ付近になるとクランクの回転に合わせてフロントディレイラーに擦る音が聞こえてました。
FC-6800はそれが全くなりません。
アウターローはたすき掛けになってしまうので、ディレイラーとの干渉音は完全には避けられないと思いますが、それもマシになりました。
満足度の高い改造でした。
ポジションを微調整
BB–サドル高 : 710mm(股下x0.866)
ブラケット–サドル先端長 : 683mm(サドル高x0.962)
サドル–ハンドル落差 : 77mm
ShimanoのULTEGRAが6800系からR8000系に刷新されたことで、6800系が在庫処分で安く出回ってます。
自分的には105でも充分かなと思いますが、折角安く手に入るのでクランクを換えようと思いました。
105 5800系とは同世代なので互換性ももちろん問題なしです。
今使ってるのは完成車のままの105 FC-5800 52–36T 170mm、所謂セミコンパクトクランクというやつです。
スプロケは完成車から12–25Tですが、105 CS-5800からULTEGRA CS-6800に換えてます。
インナー36Tはヒルクライムもインナーロー36–25Tでまぁまぁってところ。
ここぞはダンシングで乗り切るので不自由はしてませんが、もうちょい軽いギア比があったら嬉しいかなって感じです。
アウター52Tが微妙。アウタートップ52–12Tはめったに使わない。
フラットではそんな脚力もなければ、ダウンヒルはビビって回せない。
やや下りで追い風で精々13Tまでかなってところ。
12–25Tは12–13–14–15–16–17–18–19–21–23–25なんで、90rpmで30km/h近辺のギア比2.6辺り(52–20T)がないんですよね。
いつも52–21Tだと軽くて52–19Tだと重いってシチュエーションが頻繁にあります。
というわけで、前からコンパクトクランク50–34Tにしてみたいと思ってた訳です。
インナーロー34–25Tはやや軽くなるし、アウターは50–19T(ギア比2.63)が使えます。
Wiggleでなぜか50–34T(170mm)だけ他より安いので、ちょうどいい機会なので購入しました。
(9/1現在もまだ価格は変わってません)
なんか、偉そうな箱に入ってますね。流石ULTEGRAってとこか。
#スプロケはショボかったような
工具はこんな感じ。後述しますがフロントディレイラーもいじります。
・クランク取付工具 Shimano TL-FC16
クランクキャップを付け外しするやつです。
・ヘキサゴンレンチ PB 2212LH-10
左クランクの脱着に5mmを使用します。
フロントディレイラーの固定も5mmです。
ケーブルの固定は4mmです。
・トルクドライバー Park Tool ATD-1
フロントディレイラーの固定は5–7N⋅mなので6N⋅m、ケーブル固定は6–8N⋅mなのでATD-1上限の6N⋅mにします。
・PH1ドライバー PB 8190-1-80
フロントディレイラーの可動域調整に使用します。
・3/8"spヘキサゴンソケット HAZET 8801K
ヘキサゴンソケットは当然定番のHAZET。
・3/8"sqラチェットハンドル Snap-on FH936A
あるとディレイラー固定位置の微調整の緩め締めの繰り返し時に便利です。
・3/8"sqトルクレンチ 東日 MTQL40N
左クランクの固定ボルトの規定トルクは12–14N⋅mなので13N⋅mにします。
クランクの交換作業は
http://hd28with4capo.diarynote.jp/201704200000375005/
に書いた感じで。
アウターのサイズが変わるのでフロントディレイラーの再調整が必要です。
フロントディレイラーの位置極めは
http://hd28with4capo.diarynote.jp/201704232036005704/
フロントディレイラーの調整は
http://hd28with4capo.diarynote.jp/201610221737065252/
の通りです。
チェーンの長さも調整が必要なこともありますが、今回は必要ありませんでした。
さてさて、千歳まで走って来ましたが、アウター50Tはとてもいい感じです。
狙い通り17–18–19Tの辺りが使いやすくなりました。
巡行中のちょっとした勾配の変化で1Tだけシフトを上げ下げするのがクロスレシオのいいところですからね〜
高速時もトップまで使えました。
50–12Tだと50km/h超えたときに回りきってしまうシチュエーションもありましたが、100rpmほど回して乗り切れたので問題はなさそうです。
急勾配の上りはなかったので、インナー34Tはまだ分かりません。
次に手稲山にでも登ったときですかね。
クランクの剛性感も105→ULTEGRAでかなり良くなりました。
回転系なので軽量化の恩恵も大きく、回しやすくなった感じがします。
スプロケを105→ULTEGRAに変えたときは、全く差が分からなかったんですが、クランクのアップグレードは結構変わるものですね。
一番嬉しかったのは、チェーンリングが全くフレていないことですね。
FC-5800は少しフレていたので、シフトケーブルの張りを調整しても、アウタートップ付近になるとクランクの回転に合わせてフロントディレイラーに擦る音が聞こえてました。
FC-6800はそれが全くなりません。
アウターローはたすき掛けになってしまうので、ディレイラーとの干渉音は完全には避けられないと思いますが、それもマシになりました。
満足度の高い改造でした。
ポジションを微調整
BB–サドル高 : 710mm(股下x0.866)
ブラケット–サドル先端長 : 683mm(サドル高x0.962)
サドル–ハンドル落差 : 77mm
MICHELIN PRO4 Service Course V2
2017年8月17日 自転車・工具
不運なことに後タイヤがサイドカットしてしまいました。
Continental GRAND PRIX 4000SIIなんですが、まだ交換してから500km程度。
5000km持つタイヤなんで1/10しか走ってません。
タイヤ中央のバリがなくなったくらいです。
耐久性が高いのがウリの一つですがサイドカットは報告例が多数あって、サイドはあまり強くはないようです。
サイドカットがイヤならGatorSkinにしろってことですかね。
気分転換にMICHELIN PRO4に交換してみました。
グリップに定評があるけど耐久性は高くないようです。
という訳で前輪向きな感じがするので前輪に履かせます。
元々の前タイヤの4000SIIは後輪に組み替え。耐久性の良さを発揮してもらいます。
チューブはCRCだとおまけで付いてくるMICHELIN AIRSTOP A1です。
バルブ長40mmとちょっと短めですが、前ホイールならリム25mmなんで大丈夫でしょう。
重量は、PRO4 SC V2の25Cが実測224g(カタログ値215g)、AIRSTOP A1の40mmが実測95g(カタログ値96g)とそこそこスペック通りでした。
MICHELINはビードが嵌めにくいとよく言われてますが、普通に嵌まりました。
レーゼロだと嵌め易さは4000SIIとほぼ同じかと思います。
出先のパンクでも苦労はしなさそうで一安心。
タイヤ幅は25Cですが27.5mm(リム17C, 空気圧7bar)ほどあり、幅広だと言われてる4000SIIより気持ち太めでした。
100kmほど走ってみました。
グリップは思ったほど良くは感じなかったです。
ダウンヒルで40–50km/hほどでしたが、4000SIIとほぼ同じ感じ。若干効くかなくらい。
巷で言われているモチモチ感はあんまり感じなかったです。
むしろContinental Ultra SportIIの方がモチモチしてるような…(28Cだけど)
まだ新しく皮剥きが済んでないので本来の性能は出てないのかもしれません。
転がり抵抗はやはり4000SIIよりは重いです。
耐久性を考えると4000SIIは優秀なんですね。
ただ、パンクやサイドカットしてもおかしくない状況がありましたが大丈夫でした。
帰宅間際の幹線道路に看板らしきものが倒れて破損しており、夕日の木陰で直前まで見えなかったため、避けることができず前輪だけ思いっきり破片を踏んでしまいました。
新品に履き替えた途端再びサイドカットしてしまったらとドキドキしながらチェックしましたが全周無傷でした。
耐パンク/サイドカット性能はイマイチという評判ですが、運が良かったのか個人的にはいい印象になりました。
あとは耐久性と皮剥き後のグリップ性能ですかね。
Continental GRAND PRIX 4000SIIなんですが、まだ交換してから500km程度。
5000km持つタイヤなんで1/10しか走ってません。
タイヤ中央のバリがなくなったくらいです。
耐久性が高いのがウリの一つですがサイドカットは報告例が多数あって、サイドはあまり強くはないようです。
サイドカットがイヤならGatorSkinにしろってことですかね。
気分転換にMICHELIN PRO4に交換してみました。
グリップに定評があるけど耐久性は高くないようです。
という訳で前輪向きな感じがするので前輪に履かせます。
元々の前タイヤの4000SIIは後輪に組み替え。耐久性の良さを発揮してもらいます。
チューブはCRCだとおまけで付いてくるMICHELIN AIRSTOP A1です。
バルブ長40mmとちょっと短めですが、前ホイールならリム25mmなんで大丈夫でしょう。
重量は、PRO4 SC V2の25Cが実測224g(カタログ値215g)、AIRSTOP A1の40mmが実測95g(カタログ値96g)とそこそこスペック通りでした。
MICHELINはビードが嵌めにくいとよく言われてますが、普通に嵌まりました。
レーゼロだと嵌め易さは4000SIIとほぼ同じかと思います。
出先のパンクでも苦労はしなさそうで一安心。
タイヤ幅は25Cですが27.5mm(リム17C, 空気圧7bar)ほどあり、幅広だと言われてる4000SIIより気持ち太めでした。
100kmほど走ってみました。
グリップは思ったほど良くは感じなかったです。
ダウンヒルで40–50km/hほどでしたが、4000SIIとほぼ同じ感じ。若干効くかなくらい。
巷で言われているモチモチ感はあんまり感じなかったです。
むしろContinental Ultra SportIIの方がモチモチしてるような…(28Cだけど)
まだ新しく皮剥きが済んでないので本来の性能は出てないのかもしれません。
転がり抵抗はやはり4000SIIよりは重いです。
耐久性を考えると4000SIIは優秀なんですね。
ただ、パンクやサイドカットしてもおかしくない状況がありましたが大丈夫でした。
帰宅間際の幹線道路に看板らしきものが倒れて破損しており、夕日の木陰で直前まで見えなかったため、避けることができず前輪だけ思いっきり破片を踏んでしまいました。
新品に履き替えた途端再びサイドカットしてしまったらとドキドキしながらチェックしましたが全周無傷でした。
耐パンク/サイドカット性能はイマイチという評判ですが、運が良かったのか個人的にはいい印象になりました。
あとは耐久性と皮剥き後のグリップ性能ですかね。
3T ARX II TEAM
2017年7月27日 自転車・工具
Sempre Proのハンドルは交換したのですが、ステムも長いのに交換する必要があります。
元々着いているのはFSA Gossamer 100mmですが、どのくらい長くするかというのが悩ましい所です。
ハンドルだけEC90にした状態で色々握ってみた所、20–30mm程度長くするといい感じになりそうです。
ただいきなり130mmはやり過ぎになりそうな気もするので、120mmにしようかと。
125mmってのがあればいいんですけどね〜
と、調べてみると3Tは他のメーカーと採寸方法が異なるらしく、芯–芯だと数mmほど長いようです。
(角度にもよるらしいです)
ということで3Tにすることにしました。
ステムの定番メーカーで評価も高いので迷うことは特になさそうです。
スタックハイトも40mmとGossamerと同じなんで、スペーサーの増減の心配もありません。
後は角度です。
一般的な6°と、ほぼ水平になる17°があります。
(Sempre Pro 530サイズはキャスター角72°なんで、厳密には18°ないと水平にはならない)
角度によってステム長を考慮する必要があるんですが、3Tはハンドルクランプ部が同じ遠さになるようにしているみたいです。
この辺りが芯–芯でサイズ規定していない理由だと思われます。
つまり同じ120mmサイズでも6°より17°の方が実物は長い訳です。
17°の方がハンドルを限界まで下げられますが、6°の方が剛性に有利になりそうな気もします。
トップチューブはスローピングなんで見た目的には6°の方がしっくりきそう。
角度は一旦保留で。
ステムはカーボンのメリットがほぼないので、7075アルミ(超々ジュラルミン)にします。
ヘキサゴンボルトのARXとトルクスボルトのARX IIがあって、トルクスは必要ないのでARXにしようかと思いましたが、IIの120mm 6°がたまたまAmazonで67%オフになってたんで、こちらにしました。
コラムスペーサーに余裕もありハンドルもこれ以上下げる予定もないので、6°でいいでしょう。
ということで3T ARX II TEAM 120mm 6°になりました。
クランクセットのときもそうでしたが、Amazonって時々こういう謎な価格設定の商品がありますね。
1つ買ったら普通の価格になるので、在庫処分という訳でもなさそう。
(もちろんマケプレじゃないです)
安く買えてラッキーなんでこちらとしては有り難いですが。
工具はこんな感じです。
・トルクスドライバー Snap-on SDTX325
ARX IIはトルクスボルトです。
ハンドル側はT25ですのでこいつで締めます。
・ヘキサゴンレンチ HAZET 829-6 / 829-44
元のステムを外します。
トップキャップが6mm、ステムのボルトが4mmです。
・トルクドライバー Park Tool ATD-1
カーボンハンドルなんで、取り付け時はもちろんオーバートルクに注意です。
ATD-1はT25ビットも付属しています。
ハンドル側はMax 5.5N⋅mなので4.5N⋅mで固定。
・Pro-Auto ビットセット
とても小さいラチェットビットハンドルが非常に便利なビットセットです。
狭くて回しづらいところもこいつでカリカリっといけます。
今回はARX IIはコラム側のトルクスボルト1本のみT30なので、T30のビットのみ使います。
ATD-1に付けて締めます。
コラム側はMax 8N⋅mなんで6N⋅mで固定。
新ハンドル/ステムでしばらく乗ってみましたが、とてもしっくりきていい感じです!
安定して走行できています。
BB–サドル高 : 715mm(股下x0.872)
ブラケット–サドル先端長 : 684mm(サドル高x0.957)
サドル–ハンドル落差 : 80mm
で落ち着きました。
これでしばらく改造ネタはなさそうです。
元々着いているのはFSA Gossamer 100mmですが、どのくらい長くするかというのが悩ましい所です。
ハンドルだけEC90にした状態で色々握ってみた所、20–30mm程度長くするといい感じになりそうです。
ただいきなり130mmはやり過ぎになりそうな気もするので、120mmにしようかと。
125mmってのがあればいいんですけどね〜
と、調べてみると3Tは他のメーカーと採寸方法が異なるらしく、芯–芯だと数mmほど長いようです。
(角度にもよるらしいです)
ということで3Tにすることにしました。
ステムの定番メーカーで評価も高いので迷うことは特になさそうです。
スタックハイトも40mmとGossamerと同じなんで、スペーサーの増減の心配もありません。
後は角度です。
一般的な6°と、ほぼ水平になる17°があります。
(Sempre Pro 530サイズはキャスター角72°なんで、厳密には18°ないと水平にはならない)
角度によってステム長を考慮する必要があるんですが、3Tはハンドルクランプ部が同じ遠さになるようにしているみたいです。
この辺りが芯–芯でサイズ規定していない理由だと思われます。
つまり同じ120mmサイズでも6°より17°の方が実物は長い訳です。
17°の方がハンドルを限界まで下げられますが、6°の方が剛性に有利になりそうな気もします。
トップチューブはスローピングなんで見た目的には6°の方がしっくりきそう。
角度は一旦保留で。
ステムはカーボンのメリットがほぼないので、7075アルミ(超々ジュラルミン)にします。
ヘキサゴンボルトのARXとトルクスボルトのARX IIがあって、トルクスは必要ないのでARXにしようかと思いましたが、IIの120mm 6°がたまたまAmazonで67%オフになってたんで、こちらにしました。
コラムスペーサーに余裕もありハンドルもこれ以上下げる予定もないので、6°でいいでしょう。
ということで3T ARX II TEAM 120mm 6°になりました。
クランクセットのときもそうでしたが、Amazonって時々こういう謎な価格設定の商品がありますね。
1つ買ったら普通の価格になるので、在庫処分という訳でもなさそう。
(もちろんマケプレじゃないです)
安く買えてラッキーなんでこちらとしては有り難いですが。
工具はこんな感じです。
・トルクスドライバー Snap-on SDTX325
ARX IIはトルクスボルトです。
ハンドル側はT25ですのでこいつで締めます。
・ヘキサゴンレンチ HAZET 829-6 / 829-44
元のステムを外します。
トップキャップが6mm、ステムのボルトが4mmです。
・トルクドライバー Park Tool ATD-1
カーボンハンドルなんで、取り付け時はもちろんオーバートルクに注意です。
ATD-1はT25ビットも付属しています。
ハンドル側はMax 5.5N⋅mなので4.5N⋅mで固定。
・Pro-Auto ビットセット
とても小さいラチェットビットハンドルが非常に便利なビットセットです。
狭くて回しづらいところもこいつでカリカリっといけます。
今回はARX IIはコラム側のトルクスボルト1本のみT30なので、T30のビットのみ使います。
ATD-1に付けて締めます。
コラム側はMax 8N⋅mなんで6N⋅mで固定。
新ハンドル/ステムでしばらく乗ってみましたが、とてもしっくりきていい感じです!
安定して走行できています。
BB–サドル高 : 715mm(股下x0.872)
ブラケット–サドル先端長 : 684mm(サドル高x0.957)
サドル–ハンドル落差 : 80mm
で落ち着きました。
これでしばらく改造ネタはなさそうです。
EASTON EC90 SLX3
2017年7月9日 自転車・工具
Sempre Proにも慣れてきて、そろそろポジション関連をカスタマイズしていこうかなと思います。
しっくりこないのがハンドルまでの距離とハンドル幅。
買うときに530サイズと550サイズで迷ったんですが、サドル–ハンドル最大落差を考慮すると小さめ選んでた方が調整幅が広いということで後々のことを考えて530にした経緯があります。
トップチューブホリゾンタル換算長は535mmと550mmで15mmの差。
乗ってみて短いならステムを伸ばせばいいかなと。
550が長かったらステムを短くしないといけないんですが、100mmより短くするのは舵角がクイックになりすぎてあまりよくないですからね。
で、乗ってるとやっぱりハンドルが近く感じます。
というわけでステムを長くしようかと。
ただハンドル幅も狭いのでハンドルも交換ですね。
ハンドルもモノによってリーチも異なりますし、形状によってブラケット取り付け位置も変わるのでステム交換の前にまずハンドル交換を先にしました。
105の完成車のハンドルはFSAのOmega Compactです。
標準的な400mm(C–C)なんですが、ちょっと幅が狭い感じなんですよね。
というのも乗車位置から見てハの字型になっていてバーエンド部の芯–芯が400mmです。
ブラケット部は380mm(C–C)しかありません。
私は身長の割に肩幅がある方なのでちょっと窮屈です。
通勤号はLouis Garneauオリジナルハンドルで400mmなんですが、これもハの字になっててブラケット部が400mm(C–C)でバーエンド部は420mm(C–C)です。
これが幅的にはしっくりくるのでハの字でブラケット部が400mm(C–C)、バーエンド部で420mm(C–C)のやつをチョイスすることにします。
形状は通勤号のがアナトミック、Omega Compactがアナトミックシャローかなと。
通勤号のやつは下ハンの垂直部分が殆どなくしっくりこない。
Omega Compactの形状はもうちょっとカーブが緩やかだったらいいかなって感じです。
シャロー(丸ハン)も魅力的ですがドロップが大きいのがちょっとしんどそうに思えます。
アナトミックシャローとシャローの間くらいのがあれば良さそうです。
3TのErgonovaとfi’zi:k CyranoのBullかChameleonあたりが候補。
カーボンは必要ないのでアルミの7075(超々ジュラルミン)にしようかな。
と思ってたんですが、EASTONのEC90 SLX3 Proの旧型が在庫処分で定価の1/3と激安セールになってました。
形状も思ってた感じにかなり近い。しかもカーボン!
ドロップは130mmとOmega Compactの125mmよりやや大きくて良さそう。
一つ懸念は75mmとショートリーチということ。
Omega Compactが80mmなので、ただでさえ近いと感じてるリーチがさらに短くなってしまいます。
まぁコレはどうせステム交換する予定なんで別にいいか。
ということでEA90 SLX3(420mm)にしました。
ハの字型なのでブラケット部分は約400mm(C–C)です。
持った感じは思ったよりかなり軽く感じます。
カタログ値195gのところ実測205gでした。
工具はこれだけです。
・ヘキサゴンレンチ HAZET 829-4
ステムのハンドルクランプ部は4mmです。
・トルクドライバー Park Tool ATD-1
ハンドルクランプは4–6N⋅mです。
カーボンハンドルなんでオーバートルクにはくれぐれも気をつけないといけないですね。
5N⋅mで固定しました。
少し走ってみましたが、やっぱりこのハンドル幅がいいですね。
ドロップ形状もなかなかしっくりくる感じで期待以上です。
カーボンはまぁ…よく分かりませんね。
軽いけど剛性に不安は感じないのでまぁいいかなと。
ハンドル幅が拡がったので前ほど近過ぎって感じはなくなりましたが、やはりリーチは短いです。
というわけで予定通りステムも交換することにします。
しっくりこないのがハンドルまでの距離とハンドル幅。
買うときに530サイズと550サイズで迷ったんですが、サドル–ハンドル最大落差を考慮すると小さめ選んでた方が調整幅が広いということで後々のことを考えて530にした経緯があります。
トップチューブホリゾンタル換算長は535mmと550mmで15mmの差。
乗ってみて短いならステムを伸ばせばいいかなと。
550が長かったらステムを短くしないといけないんですが、100mmより短くするのは舵角がクイックになりすぎてあまりよくないですからね。
で、乗ってるとやっぱりハンドルが近く感じます。
というわけでステムを長くしようかと。
ただハンドル幅も狭いのでハンドルも交換ですね。
ハンドルもモノによってリーチも異なりますし、形状によってブラケット取り付け位置も変わるのでステム交換の前にまずハンドル交換を先にしました。
105の完成車のハンドルはFSAのOmega Compactです。
標準的な400mm(C–C)なんですが、ちょっと幅が狭い感じなんですよね。
というのも乗車位置から見てハの字型になっていてバーエンド部の芯–芯が400mmです。
ブラケット部は380mm(C–C)しかありません。
私は身長の割に肩幅がある方なのでちょっと窮屈です。
通勤号はLouis Garneauオリジナルハンドルで400mmなんですが、これもハの字になっててブラケット部が400mm(C–C)でバーエンド部は420mm(C–C)です。
これが幅的にはしっくりくるのでハの字でブラケット部が400mm(C–C)、バーエンド部で420mm(C–C)のやつをチョイスすることにします。
形状は通勤号のがアナトミック、Omega Compactがアナトミックシャローかなと。
通勤号のやつは下ハンの垂直部分が殆どなくしっくりこない。
Omega Compactの形状はもうちょっとカーブが緩やかだったらいいかなって感じです。
シャロー(丸ハン)も魅力的ですがドロップが大きいのがちょっとしんどそうに思えます。
アナトミックシャローとシャローの間くらいのがあれば良さそうです。
3TのErgonovaとfi’zi:k CyranoのBullかChameleonあたりが候補。
カーボンは必要ないのでアルミの7075(超々ジュラルミン)にしようかな。
と思ってたんですが、EASTONのEC90 SLX3 Proの旧型が在庫処分で定価の1/3と激安セールになってました。
形状も思ってた感じにかなり近い。しかもカーボン!
ドロップは130mmとOmega Compactの125mmよりやや大きくて良さそう。
一つ懸念は75mmとショートリーチということ。
Omega Compactが80mmなので、ただでさえ近いと感じてるリーチがさらに短くなってしまいます。
まぁコレはどうせステム交換する予定なんで別にいいか。
ということでEA90 SLX3(420mm)にしました。
ハの字型なのでブラケット部分は約400mm(C–C)です。
持った感じは思ったよりかなり軽く感じます。
カタログ値195gのところ実測205gでした。
工具はこれだけです。
・ヘキサゴンレンチ HAZET 829-4
ステムのハンドルクランプ部は4mmです。
・トルクドライバー Park Tool ATD-1
ハンドルクランプは4–6N⋅mです。
カーボンハンドルなんでオーバートルクにはくれぐれも気をつけないといけないですね。
5N⋅mで固定しました。
少し走ってみましたが、やっぱりこのハンドル幅がいいですね。
ドロップ形状もなかなかしっくりくる感じで期待以上です。
カーボンはまぁ…よく分かりませんね。
軽いけど剛性に不安は感じないのでまぁいいかなと。
ハンドル幅が拡がったので前ほど近過ぎって感じはなくなりましたが、やはりリーチは短いです。
というわけで予定通りステムも交換することにします。
Racing 7 LG 振れ取り
2017年6月13日 自転車・工具
通勤号にRacing 7 LGを流用してからしばらく乗ってますが、どうやら前ホイールが軽く振れてるみたいです。
ブレーキをBR-CX70にしてから、ちょっとした振れでもブレーキ音に違和感が出るのが分かるようになりました。
BR-CX70のタッチがセンシティブってことなんですかね。
工具はこれだけ。
・スポークレンチ ParkTool SW-0
超定番のスポークレンチ。普通に使いやすいですね。
Racing 7 LGのスポークは普通の2面幅3.2mmです。
この黒だけでも持ってたらほとんどのホイールに対応できるはずです。
あとはママチャリ用にSW-2(赤)くらいかな。
ちゃんとした振れ取り台は持ってないんで、フレームにつけたままやる簡易的な振れ取りです。
ブレーキシューの位置を見ながらホイールを回し、縦ブレと横ブレを確認します。
ニップルが緩んでるところだけを調整します。
縦なら出っ張ってる所、横は凹んでるところを1/8回転(45°)締める。
その都度ホイールを回して確認しながら繰り返すだけ。
これだけでも大分よくなります。
10分くらいやるとかなり振れが取れました。
まぁまだ新しいのでこんなもんでしょう。
これでさらに快適になるでしょう。
LGS-CTに元からついてた旧ホイールもそのうちやらないといけないですね。
って思ってたんですが結局ついでにやっちゃいました。
かなりグニャグニャだったんですが1時間以上かけて、大分マシになりましたよ。
ブレーキをBR-CX70にしてから、ちょっとした振れでもブレーキ音に違和感が出るのが分かるようになりました。
BR-CX70のタッチがセンシティブってことなんですかね。
工具はこれだけ。
・スポークレンチ ParkTool SW-0
超定番のスポークレンチ。普通に使いやすいですね。
Racing 7 LGのスポークは普通の2面幅3.2mmです。
この黒だけでも持ってたらほとんどのホイールに対応できるはずです。
あとはママチャリ用にSW-2(赤)くらいかな。
ちゃんとした振れ取り台は持ってないんで、フレームにつけたままやる簡易的な振れ取りです。
ブレーキシューの位置を見ながらホイールを回し、縦ブレと横ブレを確認します。
ニップルが緩んでるところだけを調整します。
縦なら出っ張ってる所、横は凹んでるところを1/8回転(45°)締める。
その都度ホイールを回して確認しながら繰り返すだけ。
これだけでも大分よくなります。
10分くらいやるとかなり振れが取れました。
まぁまだ新しいのでこんなもんでしょう。
これでさらに快適になるでしょう。
LGS-CTに元からついてた旧ホイールもそのうちやらないといけないですね。
って思ってたんですが結局ついでにやっちゃいました。
かなりグニャグニャだったんですが1時間以上かけて、大分マシになりましたよ。
CRCで買ったタイヤが届いたので早速レーゼロに組み込んで走ってみました。
ContinentalのGRAND PRIX 4000SIIです。
ドヤ顏のオバちゃんのパッケージで有名ですね。
チューブはWiggleで230円と爆安のLifeLine 18–25Cです。100gとまぁ普通な感じ。
工具はスプロケつけるのに、ロックリングツールと24mmソケットとトルクレンチだけ。
タイヤとチューブはベビーパウダーつけてはめます。
ビードも苦労せず簡単にはまりました。
MichelinはContinentalと違って苦労するらしいですね。
チューブ噛んでないか念入りに確認してから空気入れるだけ。
Max 8.5barなんで試しに前7.5bar/後8barにしてみました。
そうそう、フレの確認をしたら全くフレてませんでした。
良かった良かった。
で、新しく生まれ変わったSempre Proを試走…
予想はしてたけど、完成車に付いてきたRacing 7 LGとVittoria Zaffiroとは完全に別世界ですね。
軽すぎて通勤号とは完全に別の乗り物ですわ。
多分4kg以上違うよね… 通勤号の2/3しかない!
これで通勤したら楽やろな… 乗って行かんけど。
とにかく剛性感が段違いです。円い!真円!凄いぞレーゼロ!
それとラチェット音が静かでビックリ。ほとんど聞こえない。
爆音って聞いてたんでちょっと拍子抜け。
レー7とかアブラゼミみたいなんでね…
(追記:しばらく走ったらちょっとラチェット音が聞こえるようになりました)
あと突き上げが強くて硬い乗り味だったのが穏やかな感じになりました。
剛性感あるのに粘りがある。これがSempreのホントのポテンシャルなんかな。
Sempre Proはカーボンの中では硬めでカッチリした方だという評判ですよね。
レー7とZaffiroだと長く乗るとちょっと辛かったんですが、これなら全然平気ですね。
まぁこれは25Cにしたというのもあるかも知れません。
4000SIIはタイヤ幅も広めですからね。実際27mmありました。
レー7と4000SIIでも試してみたいけど、組み替えがちょっとめんどい。
まぁインプレはもっと詳しい人のやつの方が役に立つと思うんでこの辺にしときます。
とりあえず遠出が楽しみです。
8/18追記
後輪の4000SIIが500kmほどでサイドカットしてしまいました。
耐久性は高いけどサイドはあまり強くないかもしれないですね。残念。
どうしてもサイドカットしたくなければGatorSkinですかね。
ContinentalのGRAND PRIX 4000SIIです。
ドヤ顏のオバちゃんのパッケージで有名ですね。
チューブはWiggleで230円と爆安のLifeLine 18–25Cです。100gとまぁ普通な感じ。
工具はスプロケつけるのに、ロックリングツールと24mmソケットとトルクレンチだけ。
タイヤとチューブはベビーパウダーつけてはめます。
ビードも苦労せず簡単にはまりました。
MichelinはContinentalと違って苦労するらしいですね。
チューブ噛んでないか念入りに確認してから空気入れるだけ。
Max 8.5barなんで試しに前7.5bar/後8barにしてみました。
そうそう、フレの確認をしたら全くフレてませんでした。
良かった良かった。
で、新しく生まれ変わったSempre Proを試走…
予想はしてたけど、完成車に付いてきたRacing 7 LGとVittoria Zaffiroとは完全に別世界ですね。
軽すぎて通勤号とは完全に別の乗り物ですわ。
多分4kg以上違うよね… 通勤号の2/3しかない!
これで通勤したら楽やろな… 乗って行かんけど。
とにかく剛性感が段違いです。円い!真円!凄いぞレーゼロ!
それとラチェット音が静かでビックリ。ほとんど聞こえない。
爆音って聞いてたんでちょっと拍子抜け。
レー7とかアブラゼミみたいなんでね…
(追記:しばらく走ったらちょっとラチェット音が聞こえるようになりました)
あと突き上げが強くて硬い乗り味だったのが穏やかな感じになりました。
剛性感あるのに粘りがある。これがSempreのホントのポテンシャルなんかな。
Sempre Proはカーボンの中では硬めでカッチリした方だという評判ですよね。
レー7とZaffiroだと長く乗るとちょっと辛かったんですが、これなら全然平気ですね。
まぁこれは25Cにしたというのもあるかも知れません。
4000SIIはタイヤ幅も広めですからね。実際27mmありました。
レー7と4000SIIでも試してみたいけど、組み替えがちょっとめんどい。
まぁインプレはもっと詳しい人のやつの方が役に立つと思うんでこの辺にしときます。
とりあえず遠出が楽しみです。
8/18追記
後輪の4000SIIが500kmほどでサイドカットしてしまいました。
耐久性は高いけどサイドはあまり強くないかもしれないですね。残念。
どうしてもサイドカットしたくなければGatorSkinですかね。
通勤号 ホイール・タイヤ交換
2017年6月2日 自転車・工具
外通で購入したSempre Pro用のFulcrum Racing ZEROが届きました。
Cycling Expressは台湾なので早いですね〜
タイヤはCRCでイギリスからくるのでもう少しかかりそう。
待ち切れない所ですが、先に通勤号のホイールを換えたいと思います。
http://hd28with4capo.diarynote.jp/201705232325113229/
にも書いた通り、Sempre ProのFulcrum Racing 7 LGを流用します。
完成車についてくる、いわゆる鉄下駄ホイールでFulcrumのエントリーモデルです。
ロードバイクとしては物足りないホイールですが、一応完成車メーカーオリジナル品ではなく完組ホイールの市販品ですし、重量も1763gと一般的な鉄下駄が2000g程度ということからすると通勤用なら十分なスペックでまさに打って付けかと。
組み替え時に重さを測ってみましたが、LGS-CTの純正ホイール(Alexrim DA16のリムとShimano Soraのハブを使用したLouis Garneauオリジナル)は前990g+後1202g=2192g、Racing 7 LGは前866g+後1050g=1916gでした。
レー7はスペックより153gも重いやんけ。
でも276gの軽量化です。
Racing 7 LGは11速ホイールなので9速で使用するにはスペーサーが必要です。
Racing ZEROに付属してきたのでそれを使用します。
//このスペーサーのためにホイール届くのを待ってた
//後日確認したらSempre Proの付属品にレー7のスペーサーありました。
タイヤは低価格帯ではなかなか評判のいいContinentalのUltraSport2の28Cをチョイスしました。
チューブはWiggleで250円と爆安価格のContinental Race28 25–32Cです。
Panaracerのタイヤパウダーはボッタクリ価格なのでジョンソンのベビーパウダーを使います。
コレは有名は代用品ですね。
うーん、いい香り。幼稚園のプール思い出すわ〜
そういえば最近はベビーパウダーって使わなくなりましたよね。
ウチは3人とも使ったことないです。
ホイール換えると調整が必要になるので工具は多いです。
出先のパンクを想定してチューブ交換部分は車載工具でやってみました。
・チェーンウィップ ParkTool SR11
スプロケが空回りしない様に抑えます。
・ロックリングツール Shimano TL-LR15
スプロケのロックリングの取り外しに使用します。
・3/8"sqブレーカーバー Snap-on FH12LA
24mmのソケットをつけてロックリングツールを回します。
・3/8"sq 24mmソケット Snap-on FSM241
TL-LR15は二面幅24mmなのでそれを回します。
そもそもハブ自体がラチェットになってるので12pointじゃなくても良かったのに気づいたので、TL-LR15に合わせて6pointのものを使用。
・3/8"sq 14mmソケット Snap-on FM14
スキュワーは14mmのボルト締めなので、トルクレンチのために使用します。
・3/8"sqトルクレンチ 東日 MTQL40N
スプロケの固定はこいつで40N⋅mに締めます。
・PH1ドライバー PB 8190-1-80
ホイール交換なのでブレーキの調整が必要です。
こいつでセンター出しを行います。
・ヘキサゴンレンチ HAZET 829-4/829-5
ブレーキシューの調整は4mm、ブレーキ/シフトケーブルの固定は5mmです。
・トルクドライバー Park Tool ATD-1
6N⋅mでブレーキケーブルを固定します。
ここから車載工具です。
・14mmショートコンビレンチ STAHLWILLE 13
STAHLWILLEって品番がシンプル過ぎますよね。
13がショートコンビです。13mmじゃありません。
ちなみに14がロングコンビです。
通勤号は盗難防止でクイックリリースを使用してないので、出先でスキュワーを外すのに使用します。
STAHLWILLEのショートコンビは軽いので車載に持ってこいです。
ASAHIのライツールとかもいいかも知れません。
・マルチツール TOPEAK Hexus II
タイヤレバーを使用。
さすがに専用タイヤレバーよりは使いにくかったけど、まぁ普通に使えます。
・PWT インフレーター/CO2ボンベ
一応、流量調整出来るタイプです。
持ち運び中にボンベを固定できるネジが切ってあるすごい親切設計。
・携帯ポンプ TOPEAK Pocket Rocket MasterBlaster DX
CO2ボンベを使用するときでも、先に少しだけチューブに空気を入れておくことが必要です。
携帯ポンプでは大き目ですが軽いのでバッグに入れるにはちょうどいいかな。
作業自体は単純です。
(1)Sempre ProからRacing 7 LGを外して、スプロケも外す
(2)Racing 7 LGのタイヤとチューブをUltraSport2とRace28に交換
(3)通勤号のホイールを外して、スプロケをRacing 7 LGに移植
(1),(3)は
http://hd28with4capo.diarynote.jp/201704270048229194/
の通りです。
(2)は今回始めてCO2ボンベを使いました。
実は出先でパンクしたことないので、自宅でしかチューブ交換したことなかったんですよね。
通勤号は28Cだからパンクがなかったんですが、Sempre Proは25Cだし長い距離も乗るだろうから当然パンクはつきもの。
出先でチューブ交換できなかったらアウトですからね。
という訳で、車載工具のチェックも兼ねてCO2ボンベの練習です。
14mmコンビはバッチリ。
スキュワーは15N⋅mで締めてるので、この長さがあれば余裕で外せます。
STAHLWILLEのコンビは力かけやすいハンドルなんですよね。
問題はタイヤレバーかな。
Hexus IIのタイヤレバーはちょっと使いづらいです。
使えなくはないんですがスムーズにはいかない。
車載スペースに余裕があったら専用タイヤレバーはあった方がいいような。
Hexus IIを補助役に使うとして専用品を1本だけでも入れとくかな。
携帯ポンプは使い慣れてるやつなので全く問題なし。
CO2インフレーターはやっぱり練習しておいて正解でした。
ボンベをネジ込んで緩めていくとCO2が入る仕組みなんですが、緩めた瞬間いきなりパンパンになりました。
一瞬の出来事なんでビックリ。
出先だと焦って絶対に失敗してたと思う。
しかし、これホントに流量調整とかできるのかな?
タイヤに組み込む前に少しだけチューブに入れたりするのが可能だと説明がありましたが、加減できる自信がないです。
絶対に携帯ポンプでやった方がいいと思います。
しかし、CO2ボンベは1発でパンパンになるのでやっぱり楽ですね。
で、通勤号なんですが…
スゲーー!!!!
バリバリ進むやんけ!
漕ぎ出しの軽さといい、加速のスムーズ感といい、ココまで変わるんか!
あとガタつきがかなり減りました。タイヤが真円に近いとかいう感覚。
ブレーキもめっちゃ反応よくなりました。
ロードバイクはまずホイールを換えろっていうのが身に染みて理解できました。
ただこれは、ホイールを換えたのもあるけどタイヤの影響もかなり大きそうです。
グリップもいいし振動を吸収してるので安定しています。
古いホイールに前の13–25TスプロケとSempre Proについてた23Cのタイヤを履かせて、通勤以外で軽く走るときに使おうかと思って組んでみましたが、なんか出番なさそうです。
23Cタイヤほとんど新品だけどどうしようかな。
とりあえずRacing ZEROが今から楽しみです。
Cycling Expressは台湾なので早いですね〜
タイヤはCRCでイギリスからくるのでもう少しかかりそう。
待ち切れない所ですが、先に通勤号のホイールを換えたいと思います。
http://hd28with4capo.diarynote.jp/201705232325113229/
にも書いた通り、Sempre ProのFulcrum Racing 7 LGを流用します。
完成車についてくる、いわゆる鉄下駄ホイールでFulcrumのエントリーモデルです。
ロードバイクとしては物足りないホイールですが、一応完成車メーカーオリジナル品ではなく完組ホイールの市販品ですし、重量も1763gと一般的な鉄下駄が2000g程度ということからすると通勤用なら十分なスペックでまさに打って付けかと。
組み替え時に重さを測ってみましたが、LGS-CTの純正ホイール(Alexrim DA16のリムとShimano Soraのハブを使用したLouis Garneauオリジナル)は前990g+後1202g=2192g、Racing 7 LGは前866g+後1050g=1916gでした。
レー7はスペックより153gも重いやんけ。
でも276gの軽量化です。
Racing 7 LGは11速ホイールなので9速で使用するにはスペーサーが必要です。
Racing ZEROに付属してきたのでそれを使用します。
//このスペーサーのためにホイール届くのを待ってた
//後日確認したらSempre Proの付属品にレー7のスペーサーありました。
タイヤは低価格帯ではなかなか評判のいいContinentalのUltraSport2の28Cをチョイスしました。
チューブはWiggleで250円と爆安価格のContinental Race28 25–32Cです。
Panaracerのタイヤパウダーはボッタクリ価格なのでジョンソンのベビーパウダーを使います。
コレは有名は代用品ですね。
うーん、いい香り。幼稚園のプール思い出すわ〜
そういえば最近はベビーパウダーって使わなくなりましたよね。
ウチは3人とも使ったことないです。
ホイール換えると調整が必要になるので工具は多いです。
出先のパンクを想定してチューブ交換部分は車載工具でやってみました。
・チェーンウィップ ParkTool SR11
スプロケが空回りしない様に抑えます。
・ロックリングツール Shimano TL-LR15
スプロケのロックリングの取り外しに使用します。
・3/8"sqブレーカーバー Snap-on FH12LA
24mmのソケットをつけてロックリングツールを回します。
・3/8"sq 24mmソケット Snap-on FSM241
TL-LR15は二面幅24mmなのでそれを回します。
そもそもハブ自体がラチェットになってるので12pointじゃなくても良かったのに気づいたので、TL-LR15に合わせて6pointのものを使用。
・3/8"sq 14mmソケット Snap-on FM14
スキュワーは14mmのボルト締めなので、トルクレンチのために使用します。
・3/8"sqトルクレンチ 東日 MTQL40N
スプロケの固定はこいつで40N⋅mに締めます。
・PH1ドライバー PB 8190-1-80
ホイール交換なのでブレーキの調整が必要です。
こいつでセンター出しを行います。
・ヘキサゴンレンチ HAZET 829-4/829-5
ブレーキシューの調整は4mm、ブレーキ/シフトケーブルの固定は5mmです。
・トルクドライバー Park Tool ATD-1
6N⋅mでブレーキケーブルを固定します。
ここから車載工具です。
・14mmショートコンビレンチ STAHLWILLE 13
STAHLWILLEって品番がシンプル過ぎますよね。
13がショートコンビです。13mmじゃありません。
ちなみに14がロングコンビです。
通勤号は盗難防止でクイックリリースを使用してないので、出先でスキュワーを外すのに使用します。
STAHLWILLEのショートコンビは軽いので車載に持ってこいです。
ASAHIのライツールとかもいいかも知れません。
・マルチツール TOPEAK Hexus II
タイヤレバーを使用。
さすがに専用タイヤレバーよりは使いにくかったけど、まぁ普通に使えます。
・PWT インフレーター/CO2ボンベ
一応、流量調整出来るタイプです。
持ち運び中にボンベを固定できるネジが切ってあるすごい親切設計。
・携帯ポンプ TOPEAK Pocket Rocket MasterBlaster DX
CO2ボンベを使用するときでも、先に少しだけチューブに空気を入れておくことが必要です。
携帯ポンプでは大き目ですが軽いのでバッグに入れるにはちょうどいいかな。
作業自体は単純です。
(1)Sempre ProからRacing 7 LGを外して、スプロケも外す
(2)Racing 7 LGのタイヤとチューブをUltraSport2とRace28に交換
(3)通勤号のホイールを外して、スプロケをRacing 7 LGに移植
(1),(3)は
http://hd28with4capo.diarynote.jp/201704270048229194/
の通りです。
(2)は今回始めてCO2ボンベを使いました。
実は出先でパンクしたことないので、自宅でしかチューブ交換したことなかったんですよね。
通勤号は28Cだからパンクがなかったんですが、Sempre Proは25Cだし長い距離も乗るだろうから当然パンクはつきもの。
出先でチューブ交換できなかったらアウトですからね。
という訳で、車載工具のチェックも兼ねてCO2ボンベの練習です。
14mmコンビはバッチリ。
スキュワーは15N⋅mで締めてるので、この長さがあれば余裕で外せます。
STAHLWILLEのコンビは力かけやすいハンドルなんですよね。
問題はタイヤレバーかな。
Hexus IIのタイヤレバーはちょっと使いづらいです。
使えなくはないんですがスムーズにはいかない。
車載スペースに余裕があったら専用タイヤレバーはあった方がいいような。
Hexus IIを補助役に使うとして専用品を1本だけでも入れとくかな。
携帯ポンプは使い慣れてるやつなので全く問題なし。
CO2インフレーターはやっぱり練習しておいて正解でした。
ボンベをネジ込んで緩めていくとCO2が入る仕組みなんですが、緩めた瞬間いきなりパンパンになりました。
一瞬の出来事なんでビックリ。
出先だと焦って絶対に失敗してたと思う。
しかし、これホントに流量調整とかできるのかな?
タイヤに組み込む前に少しだけチューブに入れたりするのが可能だと説明がありましたが、加減できる自信がないです。
絶対に携帯ポンプでやった方がいいと思います。
しかし、CO2ボンベは1発でパンパンになるのでやっぱり楽ですね。
で、通勤号なんですが…
スゲーー!!!!
バリバリ進むやんけ!
漕ぎ出しの軽さといい、加速のスムーズ感といい、ココまで変わるんか!
あとガタつきがかなり減りました。タイヤが真円に近いとかいう感覚。
ブレーキもめっちゃ反応よくなりました。
ロードバイクはまずホイールを換えろっていうのが身に染みて理解できました。
ただこれは、ホイールを換えたのもあるけどタイヤの影響もかなり大きそうです。
グリップもいいし振動を吸収してるので安定しています。
古いホイールに前の13–25TスプロケとSempre Proについてた23Cのタイヤを履かせて、通勤以外で軽く走るときに使おうかと思って組んでみましたが、なんか出番なさそうです。
23Cタイヤほとんど新品だけどどうしようかな。
とりあえずRacing ZEROが今から楽しみです。
通勤号 チェーン交換
2017年5月30日 自転車・工具
チェーンリングが大きくなってチェーンが短くなってしまったので交換します。
交換してからまだ300kmも走ってないんだけどね!
KMCのX9がなかなか良かったので同じものにしようと思ったら、X9.93とX9.73があるみたいです。
公式サイトにはX9.73は載ってなくてX9.99ってのがありました。
スペック的に旧X9はX9.73が相当しそうです。
X9.93はアウターリンクのみニッケルプレートになっており、X9.99はアウター/インナーともニッケルプレートになっているみたい。
数百円の差で耐久性がアップしそうなのでX9.93にしてみました。
今回使用した工具です。
・チェーンツール ParkTool CT-4.3
チェーンは元々長めなので、規定の長さにカットする必要があります。
・マスターリンクプライヤー ParkTool MLP-1.2
KMCのチェーンはミッシングリンクで繋ぎます。
こいつで今のミッシングリンクを外して、新しいチェーンをミッシングリンクで繋ぎます。
・チェーンフック PWT CF207
チェーン作業にはもはや必須アイテム。
チェーンの長さ検討はこいつがなかったら苦労します。
新品のチェーンについてるオイルは軽くベタベタをウエスで拭きとるくらいにしてます。
入手したX9.93は116リンクでした。
アウタートップに入れてガイドプーリーとテンションプーリーが地面と垂直に並ぶ長さに調整します。
チェーンフックがあれば簡単ですね。
2リンクカットして114リンクがベストかな?
(厳密にはミッシングリンク分があるのでこの段階では113リンク)
インナー57リンク+アウター56リンク+ミッシングリンク1リンク=114リンクという訳です。
付属のミッシングリンクでチェーンを繋ぎます。
そういえばBテンションアジャストボルトの調整がまだでした。
一般まで緩めてもチェーン詰まりしないのでコレでいいかな。
シフトワイヤーを交換したのも相まって変速がとてもスムースになりました。
かなり快適ですね。
交換してからまだ300kmも走ってないんだけどね!
KMCのX9がなかなか良かったので同じものにしようと思ったら、X9.93とX9.73があるみたいです。
公式サイトにはX9.73は載ってなくてX9.99ってのがありました。
スペック的に旧X9はX9.73が相当しそうです。
X9.93はアウターリンクのみニッケルプレートになっており、X9.99はアウター/インナーともニッケルプレートになっているみたい。
数百円の差で耐久性がアップしそうなのでX9.93にしてみました。
今回使用した工具です。
・チェーンツール ParkTool CT-4.3
チェーンは元々長めなので、規定の長さにカットする必要があります。
・マスターリンクプライヤー ParkTool MLP-1.2
KMCのチェーンはミッシングリンクで繋ぎます。
こいつで今のミッシングリンクを外して、新しいチェーンをミッシングリンクで繋ぎます。
・チェーンフック PWT CF207
チェーン作業にはもはや必須アイテム。
チェーンの長さ検討はこいつがなかったら苦労します。
新品のチェーンについてるオイルは軽くベタベタをウエスで拭きとるくらいにしてます。
入手したX9.93は116リンクでした。
アウタートップに入れてガイドプーリーとテンションプーリーが地面と垂直に並ぶ長さに調整します。
チェーンフックがあれば簡単ですね。
2リンクカットして114リンクがベストかな?
(厳密にはミッシングリンク分があるのでこの段階では113リンク)
インナー57リンク+アウター56リンク+ミッシングリンク1リンク=114リンクという訳です。
付属のミッシングリンクでチェーンを繋ぎます。
そういえばBテンションアジャストボルトの調整がまだでした。
一般まで緩めてもチェーン詰まりしないのでコレでいいかな。
シフトワイヤーを交換したのも相まって変速がとてもスムースになりました。
かなり快適ですね。
通勤号のシフトケーブルにShimanoの1番安いの買ったらなかなか微妙でした。
シフトアウターって普通ケーシングがケーブルと平行なんですが、こいつはブレーキケーブルみたいに螺旋状になってるんですよね。
なんか見た感じから滑り悪そうです。
で交換するわけですが、替えたばっかりだから捨てるのもったいないよねーってことで次女のMTB LGS-J22に流用することにします。
かなりほつれてきてるのでついでにブレーキケーブルも交換します。
もちろんアウターごといきます。
さらについでに長女のCHASSEちゃんもインナーだけでも交換しときましょう。
アウター変えると「白くなくなった!ダサい!」とか言って怒りそうだし。
てことでwiggleで色々買いました。LifeLineは安くていいね。
今回の工具です。
・ケーブルカッター ParkTool CN-10
前から欲しかったカシメツールがついてるやつを導入しました。
クニペのが欲しかったけどちょっと高過ぎた。
アウターキャップもインナーエンドキャップもイケます。
いやーこれは便利ですわー
FUJIYA WC-1AHより大きくてカットも楽になりました。
アウター切るのに力が全くいらない。
インナーの切れ味はWC-1AHの方がややいいような。
アウターCN-10、インナーWC-1AHで使い分けるかな。
・ケーブルカッター FUJIYA WC-1AH
ということでインナー用で使用しました。
軽いし取り回ししやすくて使いやすい。
切れ味良くてスパっとカットできます。
やっぱりWC-1AHは優秀やね。
・ヤスリ ツボサン BRIGHT-900
カットしたアウターの断面をこいつで均します。
・オウル Snap-on 5ASAA
ヤスリがけしたアウターのライナーを整えるのに使用します。
MTBのブレーキやグリップシフトはタイコを外すのにコジる必要があるのでそれにも使用します。
・PH0ドライバー Snap-on SPP266B
グリップシフトのパネルはPH0のビスで留まってるのでこいつで外します。
・PH1ドライバー PB 8190-1-80
クロスバイクのシフトケーブルを外すのにプラキャップを外す必要があります。
ディレイラーやVブレーキの調整もコレです。
・1/4"sq 9mmソケット Snap-on TMM9
・1/4"sq ラチェットハンドル Snap-on THL936A
LGS-J22のシフトケーブルは2面幅9mmの6角ボルトで固定されています。
5mmヘキサでないのは泥詰まり防止なんですかね。
・ヘキサゴンレンチ PB 2212LH-10
・トルクドライバー Park Tool ATD-1
ケーブルの固定に5mmを使用します。
規定トルクは6–8N⋅mなのでATD-1で6N⋅mにします。
・接着剤 ボンド ウルトラ多用途SU クリヤー
通勤号のインナーケーブルの末端処理はもちろんこいつで。
子供達のは普通にエンドキャップにしました。
インナーケーブルプライヤーは2軍落ちです。
インシュロック引っ張り専用として余生を過ごしてもらう予定です。
まず通勤号から取り掛かります。
LifeLineのPerformance Gear Cable Setを使用しました。
アウターキャップがなんかカッコいい。
なんか色々入ってるけどRD用フルールの取り付け方が分からない。
Shimanoのやつとサイズ違うんだよなぁ。とりあえず無視。
それとラバーインナーケーブルシールドってのが何に使うか分からない。
取説にも書いてないし。うーん、これも無視で。
ノーズ付きキャップも入ってるけど多分ST-3500みたいな触覚ケーブルには関係ない。
エンドキャップも使わないので結局アウターキャップしか使ってないし。
取り付け手順は、
http://hd28with4capo.diarynote.jp/201705072229238771/
と同じです。
次に長女のクロスバイクのインナーケーブルです。
ブレーキケーブルはクロスバイクなのでMTB用です。
LifeLineのEssential Inner Brake Cableです。
エンドキャップが3つもついてくる。そんなにミスらないと思うけど。
ブレーキインナーケーブルはロードとMTBではタイコの形が異なり別のものなので注意です。
(ブレーキアウターケーブルは共通でイケます)
前後ともVブレーキのセンターが出ておらず、片側がすってたので調整しておきます。
シフトケーブルはST-3500についてきたやつです。
Shimanoの安モンだと思います。
シフトケーブルはロードもMTBも共通です。
交換しようと思ってインナートップに入れようと思ったら、リアがトップに入らない。
ケーブル切っても入らない。可動域がおかしいみたい。
逆にローよりかなり向こうまで動くので下手するとチェーンが落ちちゃう。
てことでトップ側、ロー側ともに可動域調整しました。
ケーブル張ったらバッチリ変速しました。
最後に次女のMTB。
ブレーキケーブルはこちらもLifeLine Essential Inner Brake CableのMTB用です。
こちらも前後ともVブレーキのセンターが出てなかったので調整。
シフトケーブルは通勤号から外したものを流用します。
これもリアがトップに入らない。
というより1–3速しか入らず、4–6速が全滅。
その辺にぶつけてリアディレイラーのハンガーを曲げてしまったのか?と心配になりましたが、結局ぶつけた時にリアディレイラーのガードが曲がっててディレイラーに干渉するのでトップまで落ちてなかっただけでした。
公園入口の柱とかにガンガンぶつけてるからね…
ディレイラーガードを戻したら無事トップに入りました。
こちらも可動域調整を行いケーブルを張ったらバッチリ変速しました。
良かった良かった。
ケーブルは定期的に交換していれば快適に乗れます。
安くて手間のかからないインナーだけでも、頻繁に新調したいですね。
//調整はメンドいけど
シフトアウターって普通ケーシングがケーブルと平行なんですが、こいつはブレーキケーブルみたいに螺旋状になってるんですよね。
なんか見た感じから滑り悪そうです。
で交換するわけですが、替えたばっかりだから捨てるのもったいないよねーってことで次女のMTB LGS-J22に流用することにします。
かなりほつれてきてるのでついでにブレーキケーブルも交換します。
もちろんアウターごといきます。
さらについでに長女のCHASSEちゃんもインナーだけでも交換しときましょう。
アウター変えると「白くなくなった!ダサい!」とか言って怒りそうだし。
てことでwiggleで色々買いました。LifeLineは安くていいね。
今回の工具です。
・ケーブルカッター ParkTool CN-10
前から欲しかったカシメツールがついてるやつを導入しました。
クニペのが欲しかったけどちょっと高過ぎた。
アウターキャップもインナーエンドキャップもイケます。
いやーこれは便利ですわー
FUJIYA WC-1AHより大きくてカットも楽になりました。
アウター切るのに力が全くいらない。
インナーの切れ味はWC-1AHの方がややいいような。
アウターCN-10、インナーWC-1AHで使い分けるかな。
・ケーブルカッター FUJIYA WC-1AH
ということでインナー用で使用しました。
軽いし取り回ししやすくて使いやすい。
切れ味良くてスパっとカットできます。
やっぱりWC-1AHは優秀やね。
・ヤスリ ツボサン BRIGHT-900
カットしたアウターの断面をこいつで均します。
・オウル Snap-on 5ASAA
ヤスリがけしたアウターのライナーを整えるのに使用します。
MTBのブレーキやグリップシフトはタイコを外すのにコジる必要があるのでそれにも使用します。
・PH0ドライバー Snap-on SPP266B
グリップシフトのパネルはPH0のビスで留まってるのでこいつで外します。
・PH1ドライバー PB 8190-1-80
クロスバイクのシフトケーブルを外すのにプラキャップを外す必要があります。
ディレイラーやVブレーキの調整もコレです。
・1/4"sq 9mmソケット Snap-on TMM9
・1/4"sq ラチェットハンドル Snap-on THL936A
LGS-J22のシフトケーブルは2面幅9mmの6角ボルトで固定されています。
5mmヘキサでないのは泥詰まり防止なんですかね。
・ヘキサゴンレンチ PB 2212LH-10
・トルクドライバー Park Tool ATD-1
ケーブルの固定に5mmを使用します。
規定トルクは6–8N⋅mなのでATD-1で6N⋅mにします。
・接着剤 ボンド ウルトラ多用途SU クリヤー
通勤号のインナーケーブルの末端処理はもちろんこいつで。
子供達のは普通にエンドキャップにしました。
インナーケーブルプライヤーは2軍落ちです。
インシュロック引っ張り専用として余生を過ごしてもらう予定です。
まず通勤号から取り掛かります。
LifeLineのPerformance Gear Cable Setを使用しました。
アウターキャップがなんかカッコいい。
なんか色々入ってるけどRD用フルールの取り付け方が分からない。
Shimanoのやつとサイズ違うんだよなぁ。とりあえず無視。
それとラバーインナーケーブルシールドってのが何に使うか分からない。
取説にも書いてないし。うーん、これも無視で。
ノーズ付きキャップも入ってるけど多分ST-3500みたいな触覚ケーブルには関係ない。
エンドキャップも使わないので結局アウターキャップしか使ってないし。
取り付け手順は、
http://hd28with4capo.diarynote.jp/201705072229238771/
と同じです。
次に長女のクロスバイクのインナーケーブルです。
ブレーキケーブルはクロスバイクなのでMTB用です。
LifeLineのEssential Inner Brake Cableです。
エンドキャップが3つもついてくる。そんなにミスらないと思うけど。
ブレーキインナーケーブルはロードとMTBではタイコの形が異なり別のものなので注意です。
(ブレーキアウターケーブルは共通でイケます)
前後ともVブレーキのセンターが出ておらず、片側がすってたので調整しておきます。
シフトケーブルはST-3500についてきたやつです。
Shimanoの安モンだと思います。
シフトケーブルはロードもMTBも共通です。
交換しようと思ってインナートップに入れようと思ったら、リアがトップに入らない。
ケーブル切っても入らない。可動域がおかしいみたい。
逆にローよりかなり向こうまで動くので下手するとチェーンが落ちちゃう。
てことでトップ側、ロー側ともに可動域調整しました。
ケーブル張ったらバッチリ変速しました。
最後に次女のMTB。
ブレーキケーブルはこちらもLifeLine Essential Inner Brake CableのMTB用です。
こちらも前後ともVブレーキのセンターが出てなかったので調整。
シフトケーブルは通勤号から外したものを流用します。
これもリアがトップに入らない。
というより1–3速しか入らず、4–6速が全滅。
その辺にぶつけてリアディレイラーのハンガーを曲げてしまったのか?と心配になりましたが、結局ぶつけた時にリアディレイラーのガードが曲がっててディレイラーに干渉するのでトップまで落ちてなかっただけでした。
公園入口の柱とかにガンガンぶつけてるからね…
ディレイラーガードを戻したら無事トップに入りました。
こちらも可動域調整を行いケーブルを張ったらバッチリ変速しました。
良かった良かった。
ケーブルは定期的に交換していれば快適に乗れます。
安くて手間のかからないインナーだけでも、頻繁に新調したいですね。
//調整はメンドいけど
通勤号改造1stインプレ
2017年5月23日 自転車・工具改造した通勤号を少し乗ったので1stインプレを。
グループセットはこんな感じです。
Shifters / Brake Lever : Shimano ST-3500 (9speed)
Front Derailleur : Shimano FD-3500 (9speed)
Rear Derailleur : Shimano RD-5701-SS (10speed)
Bottom Bracket : Shimano SM-BBR60
Crankset : Shimano FC-5800 53–39T 172.5mm (11speed)
Sprocket : Shimano CS-HG50-9 14–25T (9speed)
Chain : KMC X9 (9speed)
Brakes : Shimano BR-CX70
まず始めに、9/10/11速コンポの混合使用は問題なく、どの組み合わせでもスムーズに変速できてます。
11速チェーンリングは変速にモタついたりするかなと思いましたが至って普通です。
10速リアディレイラーはそもそも9速も対応しています。
(Shimano推奨の組み合わせではありませんので、参考にされる方はあくまでも自己責任でお願いします)
シフターは快適そのもの。
親指シフトだとずっと下ハンのまま走ることができませんでした。
通勤路は信号によるストップ&ゴーが多いので持ち替えが一々面倒くさかったんですよね。
これはもう戻れないわ〜
でも引きはやや重い印象。
これはありあわせで安モンのケーブル使ったからですね。
SORAにもぜんぜん十分ではなかった。
アウターがなんか変だったからね…
(ブレーキアウターみたいに螺旋状になってた)
もうちょいマシなものに交換予定です。
ノーマルクランクはやっぱ重いですね。
うーん、でもまぁ平地だとあまり影響なさそうですかね。
スプロケは14–25Tにしたのでかなりクロスレシオになりいい感じです。
9速を無駄なく使えそう。といってもトップはます使わないだろうな…
チェーンは短いけどあまり影響ないみたい。
せっかく注文したから届いたら交換予定です。
ブレーキは効きが良くなりましたが、感動する程は変わらないかな。
やっぱりキャリパーブレーキよりは弱いですね。
それよりも下ハンが多くなったのでブレーキがかけやすくなったのが大きいですね。
補助ブレーキは全く使ってなかったので外してハンドル周りがスッキリしました。
ブレーキパッドの調整時に気づいたんですが、後ろホイールが振れてます。
影響ないかと思ってましたがブレーキの掛かり方がフワフワする。
ブレーキがあまり効かないのはこれのせいもあるかもしれません。
数年前に前後とも振れ取りしたんですがそろそろ再調整が必要ですかね。
でも今回はコンポも交換したというのもありホイールも新調したいところ。
Sempre Proのホイールを交換したかったので、これを流用できればいいだけど。
11速ホイールなんで9速には対応(要スペーサー)しています。
ただ、Sempre Proは23Cなんですよね。
25Cは履けるだろうけど28Cは無理あるよなぁ。
通勤はやっぱり28Cくらいないとちょっと心配だし。
28C履けるかメーカーのサイトを確認することにしました。
Sempre ProのホイールはFulcrumのRacing 7です。
FulcrumのサイトをみるとRacing 7 LGというのがありました。
"TYRE WIDTH(SUGGESTED) From 25mm to 32mm"
ってアレ?
23mmが推奨外。
"The new rim is wider than before, 17C."
なるほど、モデルチェンジしてリム幅が17Cに拡がったのか。
最近流行りのワイドリムってやつですね。
LGってのがワイドリムなのか? "Large"の略かな?
じゃあ前のRacing 7は何mmなのかなと調べてると…
どうやらRacing 7は2015年に15Cから17Cになっているみたい。
私のSempre Proは2016年モデルだが…?
もう現物確認しかないよね。ってことでリム外幅を測ったら23mmジャスト。
現行モデル(17C)の外幅と一致する。
ホイールのデザインも全く同じ。ちゃんと"RACING 7 LG"ってなってますね。
現行Racing 3はまだワイドリム化されておらず15Cのままだか外幅20.5mm
ってことはRacing 7(15C)もその位のはず。
ってよくみたら622 17Cっていうシール貼ってますね…
…これワイドリムやん。
なんで23C履いてるの?メーカー推奨外なんですけど?
大丈夫なのかBianchi。
ETRTOでは1.4–2.4倍となっているので、本来なら23.8–40.8mmの間となります。
こう見ると割りと太い方は余裕がありますね。
普通はフレームのクリアランスが足りないと思いますが。
Shimanoとか一部メーカーは17Cホイールでも23Cタイヤ対応としてるようです。
調べると17Cホイールに23Cタイヤは割りとやってる人がいるみたいですね。
ただ、純正でメーカー推奨外のタイヤサイズにしてるのはどうなのかな?
まぁ、17Cだった事実は嬉しい誤算です。
15Cが廃れそうな勢いで各メーカーがワイドリム化してますからねー
15Cだと時代遅れなホイールってことになっちゃいそう。
とまぁ想定外の出来事(ラッキー?)がありましたが、Racing 7 LGは17Cだったんで28Cは普通に履けそうです。
もし15Cリムだったとしても28Cはいけることも分かりましたが。
流用できる→無駄にならない→Sempre Proのホイール交換すると通勤号も強化されて2倍お得
というわけでホイール買っちゃいました。
届くの楽しみです!
グループセットはこんな感じです。
Shifters / Brake Lever : Shimano ST-3500 (9speed)
Front Derailleur : Shimano FD-3500 (9speed)
Rear Derailleur : Shimano RD-5701-SS (10speed)
Bottom Bracket : Shimano SM-BBR60
Crankset : Shimano FC-5800 53–39T 172.5mm (11speed)
Sprocket : Shimano CS-HG50-9 14–25T (9speed)
Chain : KMC X9 (9speed)
Brakes : Shimano BR-CX70
まず始めに、9/10/11速コンポの混合使用は問題なく、どの組み合わせでもスムーズに変速できてます。
11速チェーンリングは変速にモタついたりするかなと思いましたが至って普通です。
10速リアディレイラーはそもそも9速も対応しています。
(Shimano推奨の組み合わせではありませんので、参考にされる方はあくまでも自己責任でお願いします)
シフターは快適そのもの。
親指シフトだとずっと下ハンのまま走ることができませんでした。
通勤路は信号によるストップ&ゴーが多いので持ち替えが一々面倒くさかったんですよね。
これはもう戻れないわ〜
でも引きはやや重い印象。
これはありあわせで安モンのケーブル使ったからですね。
SORAにもぜんぜん十分ではなかった。
アウターがなんか変だったからね…
(ブレーキアウターみたいに螺旋状になってた)
もうちょいマシなものに交換予定です。
ノーマルクランクはやっぱ重いですね。
うーん、でもまぁ平地だとあまり影響なさそうですかね。
スプロケは14–25Tにしたのでかなりクロスレシオになりいい感じです。
9速を無駄なく使えそう。といってもトップはます使わないだろうな…
チェーンは短いけどあまり影響ないみたい。
せっかく注文したから届いたら交換予定です。
ブレーキは効きが良くなりましたが、感動する程は変わらないかな。
やっぱりキャリパーブレーキよりは弱いですね。
それよりも下ハンが多くなったのでブレーキがかけやすくなったのが大きいですね。
補助ブレーキは全く使ってなかったので外してハンドル周りがスッキリしました。
ブレーキパッドの調整時に気づいたんですが、後ろホイールが振れてます。
影響ないかと思ってましたがブレーキの掛かり方がフワフワする。
ブレーキがあまり効かないのはこれのせいもあるかもしれません。
数年前に前後とも振れ取りしたんですがそろそろ再調整が必要ですかね。
でも今回はコンポも交換したというのもありホイールも新調したいところ。
Sempre Proのホイールを交換したかったので、これを流用できればいいだけど。
11速ホイールなんで9速には対応(要スペーサー)しています。
ただ、Sempre Proは23Cなんですよね。
25Cは履けるだろうけど28Cは無理あるよなぁ。
通勤はやっぱり28Cくらいないとちょっと心配だし。
28C履けるかメーカーのサイトを確認することにしました。
Sempre ProのホイールはFulcrumのRacing 7です。
FulcrumのサイトをみるとRacing 7 LGというのがありました。
"TYRE WIDTH(SUGGESTED) From 25mm to 32mm"
ってアレ?
23mmが推奨外。
"The new rim is wider than before, 17C."
なるほど、モデルチェンジしてリム幅が17Cに拡がったのか。
最近流行りのワイドリムってやつですね。
LGってのがワイドリムなのか? "Large"の略かな?
じゃあ前のRacing 7は何mmなのかなと調べてると…
どうやらRacing 7は2015年に15Cから17Cになっているみたい。
私のSempre Proは2016年モデルだが…?
もう現物確認しかないよね。ってことでリム外幅を測ったら23mmジャスト。
現行モデル(17C)の外幅と一致する。
ホイールのデザインも全く同じ。ちゃんと"RACING 7 LG"ってなってますね。
現行Racing 3はまだワイドリム化されておらず15Cのままだか外幅20.5mm
ってことはRacing 7(15C)もその位のはず。
ってよくみたら622 17Cっていうシール貼ってますね…
…これワイドリムやん。
なんで23C履いてるの?メーカー推奨外なんですけど?
大丈夫なのかBianchi。
ETRTOでは1.4–2.4倍となっているので、本来なら23.8–40.8mmの間となります。
こう見ると割りと太い方は余裕がありますね。
普通はフレームのクリアランスが足りないと思いますが。
Shimanoとか一部メーカーは17Cホイールでも23Cタイヤ対応としてるようです。
調べると17Cホイールに23Cタイヤは割りとやってる人がいるみたいですね。
ただ、純正でメーカー推奨外のタイヤサイズにしてるのはどうなのかな?
まぁ、17Cだった事実は嬉しい誤算です。
15Cが廃れそうな勢いで各メーカーがワイドリム化してますからねー
15Cだと時代遅れなホイールってことになっちゃいそう。
とまぁ想定外の出来事(ラッキー?)がありましたが、Racing 7 LGは17Cだったんで28Cは普通に履けそうです。
もし15Cリムだったとしても28Cはいけることも分かりましたが。
流用できる→無駄にならない→Sempre Proのホイール交換すると通勤号も強化されて2倍お得
というわけでホイール買っちゃいました。
届くの楽しみです!
LEZYNEフロアポンプ HIRAME化
2017年5月14日 自転車・工具
昨年購入した念願のフルカーボンロードは7–10bar(100–145psi)と高圧なので今まで使用していたフロアポンプ GIYO GF-55P(Max 11bar)では厳しくなってきました。
という訳でフロアポンプを新調しました。
せっかくなのでそれなりにいいものを選ぼうということで、LEZYNEのALLOY FLOOR DRIVEにしました。
GF-55Pは嫁さんのママチャリ専用でWoods(英式)固定で使うことにします。
超定番のSKSのRENNKOMPRESSORと迷ったんですがCRCは在庫切れ、Wiggleその他は取り扱いなしでした。
//国内価格は倍するんで論外
LEZYNEはCLASSIC FLOOR DRIVEとかSTEEL FLOOR DRIVEもあったんですが、スチールにするならレンコン待った方がいいよね、とALLOY FLOOR DRIVEにしました。
(CNC FLOOR DRIVEは費用対効果が見込めなかったので構想外)
頻繁に使うものには惜しみなく投資する主義なんで、KUWAHARAのHIRAMEポンプヘッドも購入しました。
通勤号は毎日乗りますからねー。
というよりHIRAMEがメインでそのためにフロアポンプを新調したって感じです。
毎回ポンプヘッドをバルブから外すのに苦労するんですよね。
ポンピング自体よりもポンプヘッドの付け外しの方が改善したときの効果でかそうですからね。
LEZYNEはABS2というネジ込み式のポンプヘッドになっています。
高圧でも外れないのがウリとか。
まずは純正ポンプヘッドのまま使ってみます。
なんか、ポンピングが重い?
GF-55Pよりは若干軽いですが、あまり改善したとは思えない。
ポンピングのたびに「キュポー、キュポー」とか鳴るし、あまりいいポンプじゃないなぁ。
ネットに上がってる使用動画とか見ても鳴いてるのないんでハズレ引いたかも。
レンコンが入荷するまで待てば良かったかなー。//今見たら入荷しとうやんけ
それと期待はしてなかったんですが、やっぱりバルブから外すときが固いですね…
というわけで、躊躇なくHIRAMEに付け替えます。
・ポンプヘッド KUWAHARA 平目2号ポンプ口金 HP-20
Presta(仏式)専用です。
Schrader(米式)、Woods(英式)のアダプターも別売りで入手可能なようです。
縦カムもありますが、定番の横カムにしてみました。
少し前までホースへの差し込み部分が真鍮剥き出しだったのが今はメッキになっているようです。
錆びなくていいですね。
使用した感じですが、縦カムの方が使いやすいかも?
ディープリムやディスクブレーキの場合は横カムじゃないと嵌められないんでしょうが。
・ホースバンド BREEZE 5.6–16mm
ヒラメにホースバンドが付属してきたんですが、外径12mm用なのか太過ぎてLEZYNEのホース(外形8mm)だとスカスカになってしまいます。
ホームセンターでバラ売りのものを買ってきました。
このホースバンドは5.6–16mmと割と適用範囲が広いので締めれます。
エアツールコーナーには2個入りパッケージ品のSK11(藤原産業)のやつしかなかったんですが、水道コーナーにバラ売りがありました。
SK11のやつもBREEZEだったんでまぁ同じでしょう。
・ポンプヘッド LEZYNE ABS-2 HP
ALLOY FLOOR DRIVEから外したやつです。
カッコいいんですが使い勝手はそこそこですね。
単体販売もありますが2000円の価値はないかな…
Schraderにも使えるんで、車用に流用するのもいいかも。
それか携帯用ポンプのアダプターでも自作してみようかな。
・ビットドライバー HAZET 810 SPC-6.3
ホースバンドのクランプはビス固定なんですが、マイナスドライバーで締めると舐めやすいです。
フィリップス(プラス)のもありますが同じことです。
ビス部分は通常1/4"の六角になっているので1/4"のレンチがあれば回せます。
インチ工具なんて持ってないよ〜ってなりそうですが、一般的なビットサイズって1/4"なんでビットドライバーがあればOKです。
元々ついていたABS-2 HPはホースを切断する必要はなく、ネジを緩めてブーツを外しホースを引っ張るだけで外せます。
まぁ単体販売ある位なんだから当たり前ですよね。
で、ホース内径はHIRAMEにはちょっときつめなのでシリコンスプレーを吹いて滑りやすくしてから捻り込みます。
あらかじめホースバンドを通しておくのを忘れずに。
ホースを伸ばしたときのポンプヘッドの向きを合わせてからホースバンドを固定します。
はみ出ている余ったバンド部分はカットしておいた方が持ったときに邪魔にならないです。
カットした後はヤスリでバリ取りしておかないと危険ですね。
HIRAMEはバルブ径に合わせてネジを微調整する必要があります。
調整のコツとしてはまずHIRAMEの構造を理解することです。
レバーを閉じることで中のパーツがリリースボタンを押し込む方向に移動します。
これによってバルブが開き空気が通るようになります。
このときゴムが出口側の金属パーツに押し潰されることでバルブを咥えこみます。
これによって圧縮された空気が漏れるのを防ぎます。
ネジはこの押し潰され量を調節する訳です。
バルブ径によって押し潰され量が変わりますからね。
締め過ぎるとレバーが固くなり、緩め過ぎると空気が漏れてしまいます。
空気が漏れないギリギリに緩くすると快適にバルブへ挿抜できるはずです。
構造を考えるとゴムが経年変化すると微調整が必要になりますね。
また、ゴムの劣化は快適性に影響があるので空気が漏れやすくなったらサッサと交換した方が良いですね。
交換用のゴムは150円位ですし。
使用のコツは、リリースボタンのネジを緩めてワンプッシュし一旦開放します。
レバーを最大まで開いてバルブに押し込まずにギリギリリリースボタンに触れる所まで入れます。
レバーを閉じればバルブが開いた状態でロックされるはずです。
空気を規定量まで入れたらレバーを開くとリリースボタンが押されてない状態に戻り、HIRAMEを簡単に抜くことができるはずです。
ウチにはPrestaは3台あるので、チューブのメーカーは合わせておいた方が便利かもしれませんね。
取りあえず最も出番の多い通勤号に合わせておくことにします。
調整を追い込んだ結果、力を掛けずとも片手でバルブからスルッと外せるようになったので空気入れが楽になりました!
という訳でフロアポンプを新調しました。
せっかくなのでそれなりにいいものを選ぼうということで、LEZYNEのALLOY FLOOR DRIVEにしました。
GF-55Pは嫁さんのママチャリ専用でWoods(英式)固定で使うことにします。
超定番のSKSのRENNKOMPRESSORと迷ったんですがCRCは在庫切れ、Wiggleその他は取り扱いなしでした。
//国内価格は倍するんで論外
LEZYNEはCLASSIC FLOOR DRIVEとかSTEEL FLOOR DRIVEもあったんですが、スチールにするならレンコン待った方がいいよね、とALLOY FLOOR DRIVEにしました。
(CNC FLOOR DRIVEは費用対効果が見込めなかったので構想外)
頻繁に使うものには惜しみなく投資する主義なんで、KUWAHARAのHIRAMEポンプヘッドも購入しました。
通勤号は毎日乗りますからねー。
というよりHIRAMEがメインでそのためにフロアポンプを新調したって感じです。
毎回ポンプヘッドをバルブから外すのに苦労するんですよね。
ポンピング自体よりもポンプヘッドの付け外しの方が改善したときの効果でかそうですからね。
LEZYNEはABS2というネジ込み式のポンプヘッドになっています。
高圧でも外れないのがウリとか。
まずは純正ポンプヘッドのまま使ってみます。
なんか、ポンピングが重い?
GF-55Pよりは若干軽いですが、あまり改善したとは思えない。
ポンピングのたびに「キュポー、キュポー」とか鳴るし、あまりいいポンプじゃないなぁ。
ネットに上がってる使用動画とか見ても鳴いてるのないんでハズレ引いたかも。
レンコンが入荷するまで待てば良かったかなー。//今見たら入荷しとうやんけ
それと期待はしてなかったんですが、やっぱりバルブから外すときが固いですね…
というわけで、躊躇なくHIRAMEに付け替えます。
・ポンプヘッド KUWAHARA 平目2号ポンプ口金 HP-20
Presta(仏式)専用です。
Schrader(米式)、Woods(英式)のアダプターも別売りで入手可能なようです。
縦カムもありますが、定番の横カムにしてみました。
少し前までホースへの差し込み部分が真鍮剥き出しだったのが今はメッキになっているようです。
錆びなくていいですね。
使用した感じですが、縦カムの方が使いやすいかも?
ディープリムやディスクブレーキの場合は横カムじゃないと嵌められないんでしょうが。
・ホースバンド BREEZE 5.6–16mm
ヒラメにホースバンドが付属してきたんですが、外径12mm用なのか太過ぎてLEZYNEのホース(外形8mm)だとスカスカになってしまいます。
ホームセンターでバラ売りのものを買ってきました。
このホースバンドは5.6–16mmと割と適用範囲が広いので締めれます。
エアツールコーナーには2個入りパッケージ品のSK11(藤原産業)のやつしかなかったんですが、水道コーナーにバラ売りがありました。
SK11のやつもBREEZEだったんでまぁ同じでしょう。
・ポンプヘッド LEZYNE ABS-2 HP
ALLOY FLOOR DRIVEから外したやつです。
カッコいいんですが使い勝手はそこそこですね。
単体販売もありますが2000円の価値はないかな…
Schraderにも使えるんで、車用に流用するのもいいかも。
それか携帯用ポンプのアダプターでも自作してみようかな。
・ビットドライバー HAZET 810 SPC-6.3
ホースバンドのクランプはビス固定なんですが、マイナスドライバーで締めると舐めやすいです。
フィリップス(プラス)のもありますが同じことです。
ビス部分は通常1/4"の六角になっているので1/4"のレンチがあれば回せます。
インチ工具なんて持ってないよ〜ってなりそうですが、一般的なビットサイズって1/4"なんでビットドライバーがあればOKです。
元々ついていたABS-2 HPはホースを切断する必要はなく、ネジを緩めてブーツを外しホースを引っ張るだけで外せます。
まぁ単体販売ある位なんだから当たり前ですよね。
で、ホース内径はHIRAMEにはちょっときつめなのでシリコンスプレーを吹いて滑りやすくしてから捻り込みます。
あらかじめホースバンドを通しておくのを忘れずに。
ホースを伸ばしたときのポンプヘッドの向きを合わせてからホースバンドを固定します。
はみ出ている余ったバンド部分はカットしておいた方が持ったときに邪魔にならないです。
カットした後はヤスリでバリ取りしておかないと危険ですね。
HIRAMEはバルブ径に合わせてネジを微調整する必要があります。
調整のコツとしてはまずHIRAMEの構造を理解することです。
レバーを閉じることで中のパーツがリリースボタンを押し込む方向に移動します。
これによってバルブが開き空気が通るようになります。
このときゴムが出口側の金属パーツに押し潰されることでバルブを咥えこみます。
これによって圧縮された空気が漏れるのを防ぎます。
ネジはこの押し潰され量を調節する訳です。
バルブ径によって押し潰され量が変わりますからね。
締め過ぎるとレバーが固くなり、緩め過ぎると空気が漏れてしまいます。
空気が漏れないギリギリに緩くすると快適にバルブへ挿抜できるはずです。
構造を考えるとゴムが経年変化すると微調整が必要になりますね。
また、ゴムの劣化は快適性に影響があるので空気が漏れやすくなったらサッサと交換した方が良いですね。
交換用のゴムは150円位ですし。
使用のコツは、リリースボタンのネジを緩めてワンプッシュし一旦開放します。
レバーを最大まで開いてバルブに押し込まずにギリギリリリースボタンに触れる所まで入れます。
レバーを閉じればバルブが開いた状態でロックされるはずです。
空気を規定量まで入れたらレバーを開くとリリースボタンが押されてない状態に戻り、HIRAMEを簡単に抜くことができるはずです。
ウチにはPrestaは3台あるので、チューブのメーカーは合わせておいた方が便利かもしれませんね。
取りあえず最も出番の多い通勤号に合わせておくことにします。
調整を追い込んだ結果、力を掛けずとも片手でバルブからスルッと外せるようになったので空気入れが楽になりました!
通勤号組立 ケーブル・バーテープ編
2017年5月7日 自転車・工具
いよいよ最終作業です。
ケーブルを張ってバーテープを巻きます。
ケーブルはShimanoにしました。
シフトケーブルは1番安いやつ。
てか、作業直前にないのに気付いてAEONに買いに行ったらこれしかなかった。
まぁSORAならこれで十分でしょ。
ブレーキケーブルはロード/MTB兼用のやつもあったんですが、せっかくULTEGRAブレーキなんでステンレスにしてみました。
ただ、ロード用だからアウターキャップが2つしか入ってない。
カンチブレーキだとアウターをフレームに引っ掛けるのでアウターキャップがもう2ついるんですよね。
家の中探したけど見つからなかったのでバラで購入しました。
1個10円なので後々のために10個ほど買っときました。←なくしそう
ちなみにロード/MTB兼用のやつは4つ入ってるみたい。
今回の工具は結構あります。
・ケーブルカッター FUJIYA WC-1AH
ケーブルカッターはいいものを使わないとアウター切る時に断面が潰れるのでダメです。
FUJIYAは国産メーカーでは定番でしょうか。
欲を言えばカシメツールがついてるもう少し大きいのが欲しいです。
・ヤスリ ツボサン BRIGHT-900
カットしたアウターの断面をこいつで均します。
・オウル Snap-on 5ASAA
ヤスリがけしたアウターのライナーを整えるのに使用します。
旧グリップ目当てで入手したのをそのまま使ってます。
・インナーケーブルプライヤー PWT ICP4585
インナーケーブルをビス締めするときにケーブルを引っ張ったまま保持できる工具です。
両手が空くので便利だという話でしたので、今回初めて使ってみましたが思ったより使いにくいですね。
使い方が下手なのかな。
・ヘキサゴンレンチ PB 2212LH-10
・トルクドライバー Park Tool ATD-1
ケーブルの固定に5mmを使用します。
規定トルクは6–8N⋅mなのでATD-1でギリギリ6N⋅mでいけます。
・接着剤 ボンド ウルトラ多用途SU クリヤー
インナーケーブルの末端処理はほつれないよう普通エンドキャップをつけるんですが、半田づけする方もいらっしゃいますよね。
ボンドが楽で手取り早いです。
ウルトラ多用途SUは万能で一家に一本あると便利です。
・はさみ PLUS フィットカットカーブ プレミアムチタン 34-553
バーテープ切るのに使います。
フィットカットカーブは有名ですね。
プレミアムチタンは糊が付着しないのでテープ関係を切るのにいいです。
・ニッパー KNIPEX 74 12 180
写真撮り忘れました。
ブレーキケーブルのアウターキャップをカシメるのに使用します。
まずアウターの長さを決めます。
普通は古いアウターと同じにすればいいですが、今回はコンポーネントも交換しましたし、ハンドルバーやステムの微調整もしてるので、同じではありません。
古いアウターを少しずつカットしながら長さを検討しました。
長さが決まったら新しいアウターをカットします。
余ったインナーの切れっぱし(なければ交換前のやつ)を通して一緒にカットした方がライナーが潰れにくくて断面がキレイになります。
ケーブルカッターで一気にスパッといきましょう。
ヤスリがけをしてライナーを整形します。
アウターの内側とインナーにオイルをつけます。
アウターはスプレータイプがやりやすいかと。NASKALUBでシュッと。
ブレーキケーブルのアウターはハンドルバーに沿って取り回しセロハンテープで固定します。
ビニールテープを使用する方もいるようですが、ビニールテープは伸びるのでセロハンテープの方がいいと思います。
インナーケーブルは取り回したら一旦ゆる〜く仮留めして先にディレイラーの調整を行います。
http://hd28with4capo.diarynote.jp/201610221737065252/
でやった手順です。
リアディレイラーも同じです。
私はケーブルを張る前に可動域を調整します。
ケーブルの張り具合を調節したら次はバーテープです。
selle ITALIAのバーテープにしてみました。
クッション性のあるものが好きです。
バーテープって巻くの難しいですよね。
巻く方向に気をつけながら巻いていきます。
こだわるならロゴの向きとか合わせます。
上ハンと下ハンで逆向きになるのでどっち向きにロゴを合わせるのがいいんでしょうか。
四苦八苦しながら何とか巻けました。
エンドテープを巻く前にビニールテープで固定します。
エンドテープにシワが寄らないように巻く方法があったら教えて欲しいです。
ブルーのバーテープで爽やかな感じになりました。
春というより夏っぽい?
通勤号改造ついに完了です!
GW明けに間に合いました。
しばらく乗ったらレビューしてみようと思います。
あ、チェーンがちょっと短いな…
チェーンリングが50→53と大分大きくなったからか。
まだ替えたばっかりだったのに…
とりあえず走れるから注文しといて届くまでガマンしよう。
ケーブルを張ってバーテープを巻きます。
ケーブルはShimanoにしました。
シフトケーブルは1番安いやつ。
てか、作業直前にないのに気付いてAEONに買いに行ったらこれしかなかった。
まぁSORAならこれで十分でしょ。
ブレーキケーブルはロード/MTB兼用のやつもあったんですが、せっかくULTEGRAブレーキなんでステンレスにしてみました。
ただ、ロード用だからアウターキャップが2つしか入ってない。
カンチブレーキだとアウターをフレームに引っ掛けるのでアウターキャップがもう2ついるんですよね。
家の中探したけど見つからなかったのでバラで購入しました。
1個10円なので後々のために10個ほど買っときました。←なくしそう
ちなみにロード/MTB兼用のやつは4つ入ってるみたい。
今回の工具は結構あります。
・ケーブルカッター FUJIYA WC-1AH
ケーブルカッターはいいものを使わないとアウター切る時に断面が潰れるのでダメです。
FUJIYAは国産メーカーでは定番でしょうか。
欲を言えばカシメツールがついてるもう少し大きいのが欲しいです。
・ヤスリ ツボサン BRIGHT-900
カットしたアウターの断面をこいつで均します。
・オウル Snap-on 5ASAA
ヤスリがけしたアウターのライナーを整えるのに使用します。
旧グリップ目当てで入手したのをそのまま使ってます。
・インナーケーブルプライヤー PWT ICP4585
インナーケーブルをビス締めするときにケーブルを引っ張ったまま保持できる工具です。
両手が空くので便利だという話でしたので、今回初めて使ってみましたが思ったより使いにくいですね。
使い方が下手なのかな。
・ヘキサゴンレンチ PB 2212LH-10
・トルクドライバー Park Tool ATD-1
ケーブルの固定に5mmを使用します。
規定トルクは6–8N⋅mなのでATD-1でギリギリ6N⋅mでいけます。
・接着剤 ボンド ウルトラ多用途SU クリヤー
インナーケーブルの末端処理はほつれないよう普通エンドキャップをつけるんですが、半田づけする方もいらっしゃいますよね。
ボンドが楽で手取り早いです。
ウルトラ多用途SUは万能で一家に一本あると便利です。
・はさみ PLUS フィットカットカーブ プレミアムチタン 34-553
バーテープ切るのに使います。
フィットカットカーブは有名ですね。
プレミアムチタンは糊が付着しないのでテープ関係を切るのにいいです。
・ニッパー KNIPEX 74 12 180
写真撮り忘れました。
ブレーキケーブルのアウターキャップをカシメるのに使用します。
まずアウターの長さを決めます。
普通は古いアウターと同じにすればいいですが、今回はコンポーネントも交換しましたし、ハンドルバーやステムの微調整もしてるので、同じではありません。
古いアウターを少しずつカットしながら長さを検討しました。
長さが決まったら新しいアウターをカットします。
余ったインナーの切れっぱし(なければ交換前のやつ)を通して一緒にカットした方がライナーが潰れにくくて断面がキレイになります。
ケーブルカッターで一気にスパッといきましょう。
ヤスリがけをしてライナーを整形します。
アウターの内側とインナーにオイルをつけます。
アウターはスプレータイプがやりやすいかと。NASKALUBでシュッと。
ブレーキケーブルのアウターはハンドルバーに沿って取り回しセロハンテープで固定します。
ビニールテープを使用する方もいるようですが、ビニールテープは伸びるのでセロハンテープの方がいいと思います。
インナーケーブルは取り回したら一旦ゆる〜く仮留めして先にディレイラーの調整を行います。
http://hd28with4capo.diarynote.jp/201610221737065252/
でやった手順です。
リアディレイラーも同じです。
私はケーブルを張る前に可動域を調整します。
ケーブルの張り具合を調節したら次はバーテープです。
selle ITALIAのバーテープにしてみました。
クッション性のあるものが好きです。
バーテープって巻くの難しいですよね。
巻く方向に気をつけながら巻いていきます。
こだわるならロゴの向きとか合わせます。
上ハンと下ハンで逆向きになるのでどっち向きにロゴを合わせるのがいいんでしょうか。
四苦八苦しながら何とか巻けました。
エンドテープを巻く前にビニールテープで固定します。
エンドテープにシワが寄らないように巻く方法があったら教えて欲しいです。
ブルーのバーテープで爽やかな感じになりました。
春というより夏っぽい?
通勤号改造ついに完了です!
GW明けに間に合いました。
しばらく乗ったらレビューしてみようと思います。
あ、チェーンがちょっと短いな…
チェーンリングが50→53と大分大きくなったからか。
まだ替えたばっかりだったのに…
とりあえず走れるから注文しといて届くまでガマンしよう。
通勤号組立 カンチブレーキ編
2017年5月6日 自転車・工具
今日はカンチブレーキを取り付けます。
BR-CX70 ULTEGRAグレードのシクロクロス用カンチブレーキです。
カンチブレーキはチドリの調整が大変なんですが、こいつはユニットリンクというものになってまして、調整がとても簡単なようです。
フロント用とリア用がありますが、ブレーキシューの取り付けが反対になっているだけでモノは同じです。
外して反対向きにつければ全く同じになります。安い方を買いましょう。
今回は同じ値段だったのでフロント用リア用を1つずつにしています。
工具はこんな感じ。
//写真使い回しなのはナイショ
・PH1ドライバー PB 8190-1-80
カンチレバーのバネを調整して左右のバランスをとります。
・ヘキサゴンレンチ PB 2212LH-10
・トルクドライバー Park Tool ATD-1
ブレーキ本体の台座への取り付けは5mm、ブレーキシューの調整は4mmです。
取り付ける前にブレーキシューのスペーサーと取り付けボルトを交換します。
元々ついているのはLサイズです。
取説に書いてある表をみて自分のバイクにあったサイズを選びます。
LGS-CTはMでした。
スペーサーを交換したら、台座に取り付けます。
バネ穴は真ん中です。
取り付けボルトの規定トルクは5–7N⋅mなので6N⋅mで締めました。
次はブレーキシューの調整です。
リムに押し当てて位置極めをし、ボルトを固定します。
6–8N⋅mですが、ブレーキケーブル通してから微調整するので仮留めでいいと思います。
リンクユニットを仮付けして完了です。
BR-CX70 ULTEGRAグレードのシクロクロス用カンチブレーキです。
カンチブレーキはチドリの調整が大変なんですが、こいつはユニットリンクというものになってまして、調整がとても簡単なようです。
フロント用とリア用がありますが、ブレーキシューの取り付けが反対になっているだけでモノは同じです。
外して反対向きにつければ全く同じになります。安い方を買いましょう。
今回は同じ値段だったのでフロント用リア用を1つずつにしています。
工具はこんな感じ。
//写真使い回しなのはナイショ
・PH1ドライバー PB 8190-1-80
カンチレバーのバネを調整して左右のバランスをとります。
・ヘキサゴンレンチ PB 2212LH-10
・トルクドライバー Park Tool ATD-1
ブレーキ本体の台座への取り付けは5mm、ブレーキシューの調整は4mmです。
取り付ける前にブレーキシューのスペーサーと取り付けボルトを交換します。
元々ついているのはLサイズです。
取説に書いてある表をみて自分のバイクにあったサイズを選びます。
LGS-CTはMでした。
スペーサーを交換したら、台座に取り付けます。
バネ穴は真ん中です。
取り付けボルトの規定トルクは5–7N⋅mなので6N⋅mで締めました。
次はブレーキシューの調整です。
リムに押し当てて位置極めをし、ボルトを固定します。
6–8N⋅mですが、ブレーキケーブル通してから微調整するので仮留めでいいと思います。
リンクユニットを仮付けして完了です。
通勤号組立 STI交換編
2017年5月5日 自転車・工具
いよいよGWも終盤。
そろそろ組み上げないとGW明けから乗っていけません。
今日はSTIの交換です。
STIはST-3500です。バルクで入手しました。
完成車用のやつで組み立てる前に取っ替えた余りなんでしょうか。
何故かシフトケーブルのインナーだけ付属していました。
工具はこんだけです。
・ヘキサゴンレンチ HAZET 829-4 / 829-5
4mmは補助ブレーキを外すのに使用します。
5mmはSTIをハンドルバーに取り付けるのに使用します。
L型のヘキサゴンレンチだと届かないのでハンドル付きかT型レンチなどが必要です。
・PH2ドライバー PB 8190
バーエンドキャップの付け外しに使用します。
・シール剥がし Zippoオイル
バーテープを剥がしたあとの糊をキレイにするのに使用します。
シール剥がしなら何でもいいんですが、私はシール剥がしにはいつもZippoのオイルを使ってます。
AZの風神雷神でもいいんですが結構高いです。
Zippoならたっぷり入ってて安いしどこでも入手できますしね。
結構、糊取り能力も高いですよー。
ハサミにこびり付いたガムテープの糊とかとるのも楽々です。
作業はまずバーテープを剥がす必要があります。
で、STIを外すんですが、この時に取り付けてあった場所をマーキングとかしていた方がいいかも知れません。
今回はついでに可変ステムやハンドルバーの微調整を行なったので、特にマーキングとかはしませんでした。
STIを外したらシール剥がしなどで綺麗に糊を取っときましょう。
で、新しいSTIを取り付けます。
取り付け位置はぶっちゃけ好みです。
下ハンのときにしっかりブレーキがかけられれば、フィーリングで決めればいいと思います。
仮留めして位置極めできたら本締めします。
指定トルクは6–8N⋅mですがトルクレンチだとソケットが入りませんでした。
なのでここは感覚でいきました。
これでやっと親指シフトとはおさらばです。
作業完了まであと一息。なんとかGW中に終えられそうか!?
作業後に暖かかったので夜ご飯に庭で肉焼いて食べました。
今年初です。やっぱり春はいいですね。
そろそろ組み上げないとGW明けから乗っていけません。
今日はSTIの交換です。
STIはST-3500です。バルクで入手しました。
完成車用のやつで組み立てる前に取っ替えた余りなんでしょうか。
何故かシフトケーブルのインナーだけ付属していました。
工具はこんだけです。
・ヘキサゴンレンチ HAZET 829-4 / 829-5
4mmは補助ブレーキを外すのに使用します。
5mmはSTIをハンドルバーに取り付けるのに使用します。
L型のヘキサゴンレンチだと届かないのでハンドル付きかT型レンチなどが必要です。
・PH2ドライバー PB 8190
バーエンドキャップの付け外しに使用します。
・シール剥がし Zippoオイル
バーテープを剥がしたあとの糊をキレイにするのに使用します。
シール剥がしなら何でもいいんですが、私はシール剥がしにはいつもZippoのオイルを使ってます。
AZの風神雷神でもいいんですが結構高いです。
Zippoならたっぷり入ってて安いしどこでも入手できますしね。
結構、糊取り能力も高いですよー。
ハサミにこびり付いたガムテープの糊とかとるのも楽々です。
作業はまずバーテープを剥がす必要があります。
で、STIを外すんですが、この時に取り付けてあった場所をマーキングとかしていた方がいいかも知れません。
今回はついでに可変ステムやハンドルバーの微調整を行なったので、特にマーキングとかはしませんでした。
STIを外したらシール剥がしなどで綺麗に糊を取っときましょう。
で、新しいSTIを取り付けます。
取り付け位置はぶっちゃけ好みです。
下ハンのときにしっかりブレーキがかけられれば、フィーリングで決めればいいと思います。
仮留めして位置極めできたら本締めします。
指定トルクは6–8N⋅mですがトルクレンチだとソケットが入りませんでした。
なのでここは感覚でいきました。
これでやっと親指シフトとはおさらばです。
作業完了まであと一息。なんとかGW中に終えられそうか!?
作業後に暖かかったので夜ご飯に庭で肉焼いて食べました。
今年初です。やっぱり春はいいですね。
通勤号組立 スプロケ交換編
2017年4月27日 自転車・工具
今回はスプロケットの交換です。
9速のままなんでそのまま使えるんですが、まだ一度も交換してません。
スプロケは消耗品なのでこの際交換です。
トップを全く使ってなかったので(ていうか2段目も使ってない)、14–25Tにしてみました。
工具はこんだけです。
・ロックリングツール Shimano TL-LR15
スプロケを固定しているロックリングの取り付け/取り外しに使用します。
ピン付きの方が使いやすいですね。
2面幅24mmで回します。
3/8"sq穴があればいいんですが、ピン付きのものはない様です。
ピンなしなら1/2"sqのものはあります。
・24mmソケット Snap-on FM24
3/8"sq 12pointのシャローソケットです。
車用に6pointも持ってますが、自転車はそんなにトルクをかける必要ないので6pointは必要ありません。
ブレーカーバーと使用するときは12pointの方が6pointよりも使いやすいです。
・3/8"sqブレーカーバー Snap-on FH12LA
至って普通のブレーカーバー。もちろん旧グリップです。
・チェーンウィップ ParkTool SR11
いわゆる小ギア抜きです。
スプロケットリムーバーとか言ったりもしますが、ロックリングツールのことを指す場合もあって混同しやすいので、個人的には使いたくない表現です。
1"の6point穴があってParkToolのロックリングツールなどが回せる様になってます。
・3/8"sqトルクレンチ 東日 MTQL40N
写真に写ってませんが、ロックリングを固定するときに使用します。
3枚目の写真のようにチェーンウィップを掛けます。
反対にかけると空回りしちゃいます。
で、力をかけると緩むはずです。
古いスプロケが外れたら、新しいスプロケを順番に嵌めるだけです。
溝に合わせる必要があります。
取り付けできたらトルクレンチで締めます。
30–50N⋅mなんで40N⋅mにしておきました。
無事スプロケも交換したので前後輪をフレームに取り付けました。
スキュワーの規定トルクは諸説ありますが、クイックリリースなら30N⋅mとか締められないし、そもそもそこまで厳密ではないはずです。
通勤号はボルト締めスキュワーなので前後輪とも15N⋅mにしておきました。
スタンドも取り付けし、やっと自立できるようになりました。
9速のままなんでそのまま使えるんですが、まだ一度も交換してません。
スプロケは消耗品なのでこの際交換です。
トップを全く使ってなかったので(ていうか2段目も使ってない)、14–25Tにしてみました。
工具はこんだけです。
・ロックリングツール Shimano TL-LR15
スプロケを固定しているロックリングの取り付け/取り外しに使用します。
ピン付きの方が使いやすいですね。
2面幅24mmで回します。
3/8"sq穴があればいいんですが、ピン付きのものはない様です。
ピンなしなら1/2"sqのものはあります。
・24mmソケット Snap-on FM24
3/8"sq 12pointのシャローソケットです。
車用に6pointも持ってますが、自転車はそんなにトルクをかける必要ないので6pointは必要ありません。
ブレーカーバーと使用するときは12pointの方が6pointよりも使いやすいです。
・3/8"sqブレーカーバー Snap-on FH12LA
至って普通のブレーカーバー。もちろん旧グリップです。
・チェーンウィップ ParkTool SR11
いわゆる小ギア抜きです。
スプロケットリムーバーとか言ったりもしますが、ロックリングツールのことを指す場合もあって混同しやすいので、個人的には使いたくない表現です。
1"の6point穴があってParkToolのロックリングツールなどが回せる様になってます。
・3/8"sqトルクレンチ 東日 MTQL40N
写真に写ってませんが、ロックリングを固定するときに使用します。
3枚目の写真のようにチェーンウィップを掛けます。
反対にかけると空回りしちゃいます。
で、力をかけると緩むはずです。
古いスプロケが外れたら、新しいスプロケを順番に嵌めるだけです。
溝に合わせる必要があります。
取り付けできたらトルクレンチで締めます。
30–50N⋅mなんで40N⋅mにしておきました。
無事スプロケも交換したので前後輪をフレームに取り付けました。
スキュワーの規定トルクは諸説ありますが、クイックリリースなら30N⋅mとか締められないし、そもそもそこまで厳密ではないはずです。
通勤号はボルト締めスキュワーなので前後輪とも15N⋅mにしておきました。
スタンドも取り付けし、やっと自立できるようになりました。
通勤号組立 ディレイラー編 その2
2017年4月23日 自転車・工具
続いてフロントディレイラーの取り付けです。
取り付け自体は単純です。
シートチューブに固定するだけ。
大変なのは位置合わせです。
チェーンリングのアウターと平行かつギアから1–3mmの位置に固定しなければなりません。
ここを怠ると変速がスムーズにいかなくなってしまいます。
まずはズレない程度に軽めに締めて位置決めします。
ガイドシールが貼っているのでそれを目安にしてもいいですが、意外と見づらいので剥がしてしまって直尺で確認するのがやりやすいと思います。
位置決めが終わったら本締めします。
締めるときに位置決めした位置からズレないようにしましょう。
5–7N⋅mなのでATD-1で6N⋅mで締めました。
ディレイラーの調整はシフトケーブルを張ってからなので、今回はこれで完了です。
取り付け自体は単純です。
シートチューブに固定するだけ。
大変なのは位置合わせです。
チェーンリングのアウターと平行かつギアから1–3mmの位置に固定しなければなりません。
ここを怠ると変速がスムーズにいかなくなってしまいます。
まずはズレない程度に軽めに締めて位置決めします。
ガイドシールが貼っているのでそれを目安にしてもいいですが、意外と見づらいので剥がしてしまって直尺で確認するのがやりやすいと思います。
位置決めが終わったら本締めします。
締めるときに位置決めした位置からズレないようにしましょう。
5–7N⋅mなのでATD-1で6N⋅mで締めました。
ディレイラーの調整はシフトケーブルを張ってからなので、今回はこれで完了です。
通勤号組立 ディレイラー編 その1
2017年4月22日 自転車・工具
今回はディレイラーを組み付けます。
これまたセール品なので、フロントがSORA、リアが105と前後バラバラです。
使用工具です。
・トルクドライバー Park Tool ATD-1
自転車イジるならとても便利なトルク管理ツールです。
4–6N⋅mとレンジは狭いですが、普段はコレ1本でまかなえます。
詳しくは
http://hd28with4capo.diarynote.jp/201610221737065252/
に書いてます。
・3/8"sqヘキサゴンソケット HAZET 8801K
当然HAZET。信頼度が違います。
・AZ チッコイグリースガン+自転車用グリース
変わった商品名ですが小型で便利です。
600円程度とかなり安いです。
ガン単体で買っても20gグリースのセットで買っても殆ど値段変わりません。
#シリコングリースのセットは流石にちょっと値が張ります。
セットの中で自転車用グリースとは同社のウレアグリースの様です。
ウレアグリースはそこそこ高級な部類になるのでお得ですね!
・ヘキサゴンレンチ PB 2212LH-10
PBのショートヘッドは力掛けやすくて使いやすいです。
レインボーはハゲるので好きじゃないです。
・3/8"sqトルクレンチ 東日 MTQL40N
リアディレイラーをハンガーに固定するのはATD-1ではトルク不足なのでこれを使います。
・直尺 シンワ 150mm
フロントディレイラーの固定時に使用します。
定規だとちょっとやりづらいです。
まず簡単なリアディレイラーから作業を行いました。
ハンガーに固定するだけです。
注意するのはBテンションアジャストボルトを引っ掛けないようにするだけです。
トルクは8–10N⋅mなので5mmソケットとMTQL40Nで9N⋅mで固定しました。
シフトケーブルはSTIを交換してからなのでこれで完了。
次回はフロントディレイラーです。
これまたセール品なので、フロントがSORA、リアが105と前後バラバラです。
使用工具です。
・トルクドライバー Park Tool ATD-1
自転車イジるならとても便利なトルク管理ツールです。
4–6N⋅mとレンジは狭いですが、普段はコレ1本でまかなえます。
詳しくは
http://hd28with4capo.diarynote.jp/201610221737065252/
に書いてます。
・3/8"sqヘキサゴンソケット HAZET 8801K
当然HAZET。信頼度が違います。
・AZ チッコイグリースガン+自転車用グリース
変わった商品名ですが小型で便利です。
600円程度とかなり安いです。
ガン単体で買っても20gグリースのセットで買っても殆ど値段変わりません。
#シリコングリースのセットは流石にちょっと値が張ります。
セットの中で自転車用グリースとは同社のウレアグリースの様です。
ウレアグリースはそこそこ高級な部類になるのでお得ですね!
・ヘキサゴンレンチ PB 2212LH-10
PBのショートヘッドは力掛けやすくて使いやすいです。
レインボーはハゲるので好きじゃないです。
・3/8"sqトルクレンチ 東日 MTQL40N
リアディレイラーをハンガーに固定するのはATD-1ではトルク不足なのでこれを使います。
・直尺 シンワ 150mm
フロントディレイラーの固定時に使用します。
定規だとちょっとやりづらいです。
まず簡単なリアディレイラーから作業を行いました。
ハンガーに固定するだけです。
注意するのはBテンションアジャストボルトを引っ掛けないようにするだけです。
トルクは8–10N⋅mなので5mmソケットとMTQL40Nで9N⋅mで固定しました。
シフトケーブルはSTIを交換してからなのでこれで完了。
次回はフロントディレイラーです。
通勤号組立 BB・クランク編
2017年4月19日 自転車・工具
雪も解けてきたのでそろそろ自転車も組まないといけないですね。
今回はBBとクランクの取り付けです。
http://hd28with4capo.diarynote.jp/201611061624156171/
で書きましたが、安く購入できた105のノーマルクランクです。
使用工具はこんな感じ。
・3/8"sqヘキサゴンソケット HAZET 8801K
トルクレンチで締めるのでソケットを使用します。
ヘキサゴンソケットはHAZET一択。選択の余地なし。
左クランクを固定するのに5mmを使用します。
・BBツール Park Tool BBT-69
3/8"sqが空いててトルクレンチが使えますし、ローレットがあるのがいい感じです。
・PWT SM-BBR60アダプター(加工あり)
SM-BBR60はホローテックIIですが通常よりも一回り小型です。
なのでBBツールにアダプターを咬ませる必要があります。
SM-BBR60にTL-FC25というアダプターが付属してくるんですが、これシマノ純正のBBツールにしか嵌まらないんですよね。
BBT-69はカンパニョーロとかにも対応した汎用品なんで、アダプターを加工する必要があります。
TL-FC25はかなり削らないと嵌まらないので、比較的形状の近いPWTのアダプターを入手して削りました。
いやーそれでもかなり大変ですね、コレ。
労力考えると素直にSM-BBR60用のBBT-59を買った方がいいと思います。
まぁ、BB表面に金属で直だとキズが付きそうなんでプラで保護できると思えば無駄でもないか。
・クランク取付工具 Shimano TL-FC16
クランクキャップを付け外しするやつです。
マイナスドライバーとかで代用できるそうですが、200円程度のもんなんで買っといても別に痛くないのでは。
・3/8"sqラチェットハンドル Snap-on FH936A
http://hd28with4capo.diarynote.jp/201404061529112373/
で紹介してるように旧グリップに打ち替えています。
バネも短いものに交換して空転トルクも軽くしてあります。
こちらはF836と同じグリップサイズのタイヤレバーTR118からの移植です。
通常FH936AはFH80同様シャフトが長いらしいんですが、私のは切断すべくグリップを外したら短かったので旧グリップがそのまま入りました。
FH936AはFH936とグリップ以外は同じなので、金型変更するまでFH936のものをそのまま使用してしばらく生産してたんでしょうか。
FH936改とはグリップの個体差なのかこちらの方が数mmグリップが長くて、トルクレンチとほぼ同じ位置で握れるのがポイントです。
・3/8"sqトルクレンチ 東日 MTQL40N
オートバイク用のワイドレンジのやつです。
ワイドレンジなので精度は±5%と通常のQL/QL-MHシリーズに劣りますが、5–40N⋅mなので自転車ならコレ1本で大体カバーできます。
・無反動ハンマー PB 300/2
PBはドライバーやヘキサゴンレンチで有名ですが、このハンマーも軽くて反動もないので快適です。
ヘッドも交換できるので1本持ってて損はないと思います。
・WAKO’S スレッドコンパウンド
BBはカジリやすいのでコレを塗っときましょう。
アルミフレームは特に電蝕しやすいです。
取り外しは大変でしたが、取り付けはそんなに難しい作業はありません。
ホローテックIIは35–50N⋅mですので左ワンはトルクレンチで40N⋅mで固定しました。
残念ながら逆回しのトルクレンチは持ってないので右ワンはラチェットハンドルで締めます。
FH936だとMTQL40Nとほぼ同じ位置でグリップできるので感覚で大体同じくらいに締めることができます。
右クランクを取り付けるときはハンマーで軽く叩く必要があります。
キズがつかないようにあて布をしましょう。
左クランクも嵌め込んだらクランクキャップを取り付けます。
なんか指定トルク(0.7–1.5N⋅m)があるようですがどうやって測るのか。
気にせずテキトーに締めます。それとツメを倒すのを忘れないように。
固定ボルトの指定トルクは12–14N⋅mなので13N⋅mにしておきました。
サクサクっと作業完了。簡単ですね。
クランクを変えると随分印象が変わりますね。
105クランクはやっぱりカッコいい!テンション上がります!
11sとか書いてて高級感も出ました。まぁ9速のままなんですが。
今回はBBとクランクの取り付けです。
http://hd28with4capo.diarynote.jp/201611061624156171/
で書きましたが、安く購入できた105のノーマルクランクです。
使用工具はこんな感じ。
・3/8"sqヘキサゴンソケット HAZET 8801K
トルクレンチで締めるのでソケットを使用します。
ヘキサゴンソケットはHAZET一択。選択の余地なし。
左クランクを固定するのに5mmを使用します。
・BBツール Park Tool BBT-69
3/8"sqが空いててトルクレンチが使えますし、ローレットがあるのがいい感じです。
・PWT SM-BBR60アダプター(加工あり)
SM-BBR60はホローテックIIですが通常よりも一回り小型です。
なのでBBツールにアダプターを咬ませる必要があります。
SM-BBR60にTL-FC25というアダプターが付属してくるんですが、これシマノ純正のBBツールにしか嵌まらないんですよね。
BBT-69はカンパニョーロとかにも対応した汎用品なんで、アダプターを加工する必要があります。
TL-FC25はかなり削らないと嵌まらないので、比較的形状の近いPWTのアダプターを入手して削りました。
いやーそれでもかなり大変ですね、コレ。
労力考えると素直にSM-BBR60用のBBT-59を買った方がいいと思います。
まぁ、BB表面に金属で直だとキズが付きそうなんでプラで保護できると思えば無駄でもないか。
・クランク取付工具 Shimano TL-FC16
クランクキャップを付け外しするやつです。
マイナスドライバーとかで代用できるそうですが、200円程度のもんなんで買っといても別に痛くないのでは。
・3/8"sqラチェットハンドル Snap-on FH936A
http://hd28with4capo.diarynote.jp/201404061529112373/
で紹介してるように旧グリップに打ち替えています。
バネも短いものに交換して空転トルクも軽くしてあります。
こちらはF836と同じグリップサイズのタイヤレバーTR118からの移植です。
通常FH936AはFH80同様シャフトが長いらしいんですが、私のは切断すべくグリップを外したら短かったので旧グリップがそのまま入りました。
FH936AはFH936とグリップ以外は同じなので、金型変更するまでFH936のものをそのまま使用してしばらく生産してたんでしょうか。
FH936改とはグリップの個体差なのかこちらの方が数mmグリップが長くて、トルクレンチとほぼ同じ位置で握れるのがポイントです。
・3/8"sqトルクレンチ 東日 MTQL40N
オートバイク用のワイドレンジのやつです。
ワイドレンジなので精度は±5%と通常のQL/QL-MHシリーズに劣りますが、5–40N⋅mなので自転車ならコレ1本で大体カバーできます。
・無反動ハンマー PB 300/2
PBはドライバーやヘキサゴンレンチで有名ですが、このハンマーも軽くて反動もないので快適です。
ヘッドも交換できるので1本持ってて損はないと思います。
・WAKO’S スレッドコンパウンド
BBはカジリやすいのでコレを塗っときましょう。
アルミフレームは特に電蝕しやすいです。
取り外しは大変でしたが、取り付けはそんなに難しい作業はありません。
ホローテックIIは35–50N⋅mですので左ワンはトルクレンチで40N⋅mで固定しました。
残念ながら逆回しのトルクレンチは持ってないので右ワンはラチェットハンドルで締めます。
FH936だとMTQL40Nとほぼ同じ位置でグリップできるので感覚で大体同じくらいに締めることができます。
右クランクを取り付けるときはハンマーで軽く叩く必要があります。
キズがつかないようにあて布をしましょう。
左クランクも嵌め込んだらクランクキャップを取り付けます。
なんか指定トルク(0.7–1.5N⋅m)があるようですがどうやって測るのか。
気にせずテキトーに締めます。それとツメを倒すのを忘れないように。
固定ボルトの指定トルクは12–14N⋅mなので13N⋅mにしておきました。
サクサクっと作業完了。簡単ですね。
クランクを変えると随分印象が変わりますね。
105クランクはやっぱりカッコいい!テンション上がります!
11sとか書いてて高級感も出ました。まぁ9速のままなんですが。
通勤号解体 フレーム清掃編
2016年12月18日 自転車・工具
リフレクタやU字ロックのブラケットなどの小物類がまだ残っていたのでPH2ドライバーで外しました。
フレームから各パーツが外れたので、今回は酷く汚れたフレームを清掃していきます。
ハンドルは外すとフレームを立てられなくなるので付けたままです。
室内でやるので水をぶっかけてジャブジャブやったりはしません。
どうせ水かけても汚れ取れませんし…
まぁケミカル類に頼ることになります。
使うケミカルはこんな感じ。
・シンプルグリーン
知る人ぞ知る、油汚れに強い味方です。
キッチンの換気扇とかに使ってる人も多いんじゃないでしょうか。
これ、基本薄めて使うはずなんですが、スプレーボトルで売ってます。なんでやねん。
詰め替え用を買って、空のスプレーボトルを別途用意する方が使い易いです。
稀釈率が目盛りで分かるようになっている専用ボトルも売ってますが、私はただの空ボトルに400円も出せないです。
マジックリンの空ボトルで代用してます。
ガンコな油汚れは稀釈率1/2なんでこれでいいかな。
もっと薄めて使うような箇所ならジョイとかでもいいかも。
・WAKO’S フォーミングマルチクリーナー
自転車クリーナーではこれが最強なんではないでしょうか。
クリンビューのノータッチって知ってますかね?
車のタイヤにスプレーするだけで汚れを落として真っ黒になるとかいう、ウソみたいなCMを昔バンバンやってました。
いや、ホントに真っ黒になるんですよ。
私は今でも愛用してます。お手軽ですしね。
あれに似てる感じって言ったら伝わりますかね。
こいつの場合、拭き取りは必要なんですが。
シンプルグリーンでも落とすのに苦労する箇所とかはこいつでいきます。
垂れないように配慮すれば室内でも割と使えます。
ネックはWAKO’Sにありがちな値段の高さですね。
でも価格に見合った性能で間違いなくオススメ。
・AZ 強力パーツクリーナー
手が届きづらい入り組んだ箇所に溜まった泥はこいつで拭き飛ばします。
今回は室内なんでバットで受けながら使用しましたが、あまり出番なし。
ケミカルで汚れを溶かしながらマイクロファイバークロスで拭き取ります。
・LEC 激落ちクロス
これが安くていいんじゃないでしょうか。1枚60円です。
1回でかなり汚れるので使い捨てできる価格はいいですね。
あとはAmazonベーシックも良さげですね。
100均でも2枚で100円のもありますが、質はそれなりでしょうか。
かなり汚れたので時間かかりましたが、何とかかんとかキレイになりました。
前のBB周りのひどい汚れの写真と比較すると、雲泥の差です。
キレイになると気持ちいいですね。
フレームから各パーツが外れたので、今回は酷く汚れたフレームを清掃していきます。
ハンドルは外すとフレームを立てられなくなるので付けたままです。
室内でやるので水をぶっかけてジャブジャブやったりはしません。
どうせ水かけても汚れ取れませんし…
まぁケミカル類に頼ることになります。
使うケミカルはこんな感じ。
・シンプルグリーン
知る人ぞ知る、油汚れに強い味方です。
キッチンの換気扇とかに使ってる人も多いんじゃないでしょうか。
これ、基本薄めて使うはずなんですが、スプレーボトルで売ってます。なんでやねん。
詰め替え用を買って、空のスプレーボトルを別途用意する方が使い易いです。
稀釈率が目盛りで分かるようになっている専用ボトルも売ってますが、私はただの空ボトルに400円も出せないです。
マジックリンの空ボトルで代用してます。
ガンコな油汚れは稀釈率1/2なんでこれでいいかな。
もっと薄めて使うような箇所ならジョイとかでもいいかも。
・WAKO’S フォーミングマルチクリーナー
自転車クリーナーではこれが最強なんではないでしょうか。
クリンビューのノータッチって知ってますかね?
車のタイヤにスプレーするだけで汚れを落として真っ黒になるとかいう、ウソみたいなCMを昔バンバンやってました。
いや、ホントに真っ黒になるんですよ。
私は今でも愛用してます。お手軽ですしね。
あれに似てる感じって言ったら伝わりますかね。
こいつの場合、拭き取りは必要なんですが。
シンプルグリーンでも落とすのに苦労する箇所とかはこいつでいきます。
垂れないように配慮すれば室内でも割と使えます。
ネックはWAKO’Sにありがちな値段の高さですね。
でも価格に見合った性能で間違いなくオススメ。
・AZ 強力パーツクリーナー
手が届きづらい入り組んだ箇所に溜まった泥はこいつで拭き飛ばします。
今回は室内なんでバットで受けながら使用しましたが、あまり出番なし。
ケミカルで汚れを溶かしながらマイクロファイバークロスで拭き取ります。
・LEC 激落ちクロス
これが安くていいんじゃないでしょうか。1枚60円です。
1回でかなり汚れるので使い捨てできる価格はいいですね。
あとはAmazonベーシックも良さげですね。
100均でも2枚で100円のもありますが、質はそれなりでしょうか。
かなり汚れたので時間かかりましたが、何とかかんとかキレイになりました。
前のBB周りのひどい汚れの写真と比較すると、雲泥の差です。
キレイになると気持ちいいですね。
通勤号解体 ブレーキ編
2016年11月16日 自転車・工具
そういえばまだブレーキを外してなかったです。
ディレイラーのときに一緒にケーブル切っとけばよかったですね。
今回の工具です。
・ケーブルカッター FUJIYA WC-1AH
まずケーブルを切らないと始まりません。
LGS-CTはカンチレバーブレーキです。
今回アーチワイヤーは切らずに取っておきます。
・ヘキサゴンレンチ Wera 950SPKL/9SM
ブレーキシューのボルト、アーチワイヤーを引っ掛けるところ、カンチブレーキを台座から外すのは全て5mmです。
・スタンダードコンビレンチ Snap-on OEXM100
TEKTRO CR520の場合、ブレーキケーブルを外すのは10mmのナットを緩めます。
5mmのヘキサゴンを回してはいけません。
ブレーキを台座から外す前に先にブレーキシューを外す方がやりやすいです。
台座がら外してしまうとブレーキシューの固定ボルトを回すのに力が掛けづらいので。
固着気味なので5-56を噴いておきます。
外したらブレーキダストで真っ黒だったのでキレイに洗浄しておきました。
ディレイラーのときに一緒にケーブル切っとけばよかったですね。
今回の工具です。
・ケーブルカッター FUJIYA WC-1AH
まずケーブルを切らないと始まりません。
LGS-CTはカンチレバーブレーキです。
今回アーチワイヤーは切らずに取っておきます。
・ヘキサゴンレンチ Wera 950SPKL/9SM
ブレーキシューのボルト、アーチワイヤーを引っ掛けるところ、カンチブレーキを台座から外すのは全て5mmです。
・スタンダードコンビレンチ Snap-on OEXM100
TEKTRO CR520の場合、ブレーキケーブルを外すのは10mmのナットを緩めます。
5mmのヘキサゴンを回してはいけません。
ブレーキを台座から外す前に先にブレーキシューを外す方がやりやすいです。
台座がら外してしまうとブレーキシューの固定ボルトを回すのに力が掛けづらいので。
固着気味なので5-56を噴いておきます。
外したらブレーキダストで真っ黒だったのでキレイに洗浄しておきました。
1 2